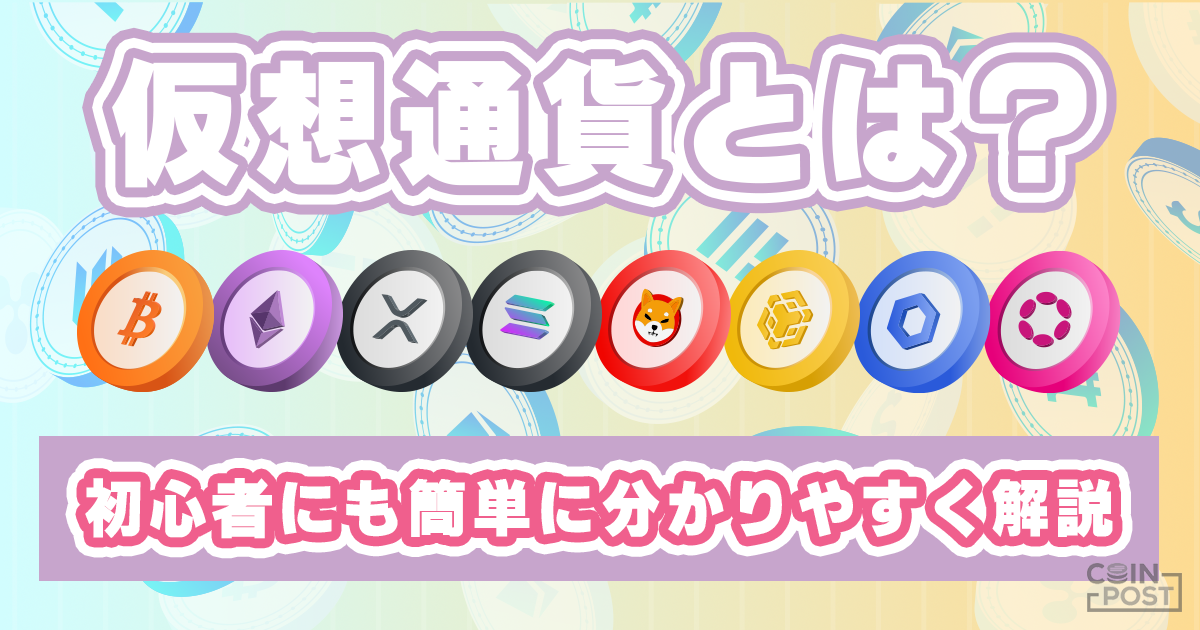
仮想通貨(暗号資産)は、年を追うごとに大きく成長していっている市場で、2024年には世界で500兆円規模に。インターネット上で使える新しい形のデジタルマネーとして国内外から大きな注目を集めています。
一方で、仮想通貨は従来の金融商品やお金とは異なる特徴を持つため、不明点も多く、投資に踏み出せないという方も多いでしょう。
そこで、本記事では仮想通貨の基礎から活用方法まで、初心者の方でも理解できるよう分かりやすく解説します。
仮想通貨の基本知識

仮想通貨とは、ブロックチェーン技術を使ったインターネット上で取引される新しいデジタル通貨です。
仮想通貨と暗号資産の区別は呼び方が異なるだけで同じものです。仮想通貨は法改正により2020年5月から「暗号資産」が正式名称になりました。
仮想通貨とは?

先に挙げた通り、仮想通貨とはインターネット上でやり取りされるデジタル資産です。代表的なものにビットコイン(BTC)やイーサリアム(ETH)があり、2万種類を超える銘柄があり、日々新たな銘柄が誕生しています。
仮想通貨は円やドルといった法定通貨のように、物理的な実体が存在しません。また、国家によって価値が裏付けられているものではなく、インターネット上でやりとりされる電子データです。
しかし、仮想通貨は法定通貨で行うほぼすべてのことができます。また、法定通貨とも交換できることが仮想通貨の経済的価値の土台となっていると考えられます。
仮想通貨と電子マネーの違い
 仮想通貨とよく混同されやすいのが、電子マネーです。
紙幣や硬貨ではない点は仮想通貨と同じですが、異なる点もあります。概要については下記表のようなものです。
仮想通貨とよく混同されやすいのが、電子マネーです。
紙幣や硬貨ではない点は仮想通貨と同じですが、異なる点もあります。概要については下記表のようなものです。
| 電子マネー | 仮想通貨 | |
|---|---|---|
| 具体例 |
|
|
| 管理主体 | 発行企業 | 基本的にない |
| 価値の変動 | 少ない | 大きい |
| 個人間送金 | 不可 | 可 |
電子マネーは必ず発行主体が存在し、発行主体が価値に裏づけされており、価値は一定です。また、原則として換金することができず、不特定の人との取引にも利用できません。
一方、仮想通貨は発行主体や管理者が基本的に存在せず、銘柄ごとに価格が大きく変動することもあります。また、法定通貨に換金することができ、銀行などの金融機関の仲介なしに直接やり取りすることが可能です。
ブロックチェーン技術

ブロックチェーンとは、仮想通貨の基盤技術となるものです。
取引履歴を暗号技術で連鎖的につなぎ、データを分散管理することで、その取引記録を安全に管理しています。
特定の管理者を必要とせず、参加者全員でデータを共有・管理することで、システム障害や不正に強い堅牢性を実現。
「分散型台帳技術」とも呼ばれ、情報をブロック単位で時系列に記録し、改ざんが極めて困難な特徴を持ちます。
台帳の全部または一部を参加者間で共有し、誰が、いつ、どのような情報を記録したのかを透明性高く管理できる特性から、銀行業務や企業間取引など、幅広い分野での活用が期待されています。
ビットコインについて

ビットコインは、2009年にサトシ・ナカモトによって開発された、世界初のブロックチェーン技術を活用したデジタル通貨です。従来の法定通貨と異なり、中央銀行などの管理者が存在せず、P2Pネットワークによる分散型システムで運営されている点が特徴です。
発行上限が2,100万枚と定められており、インフレーションを防ぐ設計となっています。また、国境を越えた送金や決済が可能で、スマートフォンやパソコンを通じて世界中で利用できます。
現在、仮想通貨市場において約280兆円と最大の時価総額、全銘柄中トップを誇り、仮想通貨の代表格としての地位を確立しています。
ブロックチェーン技術により、取引の透明性と安全性が確保され、次世代の決済手段として注目を集めています。
仮想通貨の活用方法

仮想通貨という言葉を聞くと、使い道は資産として保有するだけと思われる方もいるかもしれませんが、資産以外にも様々な使い道が存在します。
一般的に知られている「投資」としての活用方法も含めて、ひとつひとつ具体的に解説していきます。
仮想通貨投資

仮想通貨は、投資・資産運用の対象として広く認知されています。特にビットコインは2024年11月に約1500万円の最高値を記録し、高いリターンポテンシャルを示しました。
取引方法には、実際の仮想通貨の受け渡しを行う現物取引と、証拠金を活用して取引できるレバレッジ取引があります。ただし、高いリターンが期待できる一方で、それに応じたリスクも存在することを理解しておく必要があります。
決済・送金

仮想通貨の活用方法として、決済と送金の機能があります。送金面では、ブロックチェーン技術を活用することで、国内外問わず低コストかつスピーディーな取引が可能です。
決済においては、2017年の改正資金決済法により国内でも正式な決済手段として認められ、ビックカメラなどの大手小売店での利用が可能になりました。
店舗側にとっては、クレジットカード決済と比べて手数料が5分の1程度に抑えられ、即日入金というメリットがあります。また、利用者側も為替手数料を気にすることなく、世界中のサイトで決済できる利点があります。
特に途上国など、銀行口座の保有が困難な地域においては、インターネット環境さえあれば利用できる仮想通貨の送金・決済システムが、新たな金融インフラとして期待されています。
関連:金融庁、暗号資産規制の抜本的見直しへ 金商法適用も視野
NFT
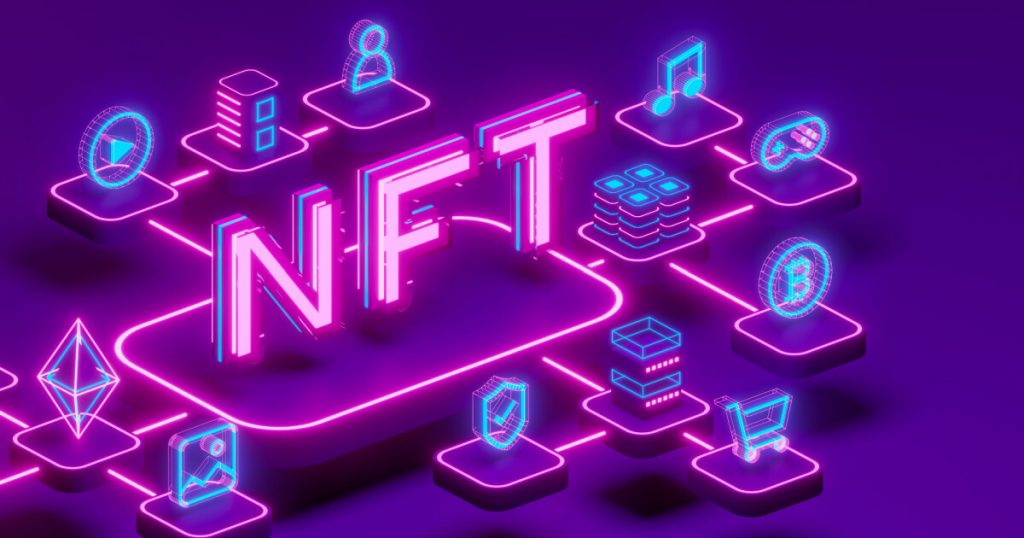
仮想通貨の新たな活用事例として、NFT(Non-Fungible Token)取引における決済手段があります。NFTは、デジタルアートやメタバース内の資産など、デジタル上の代替不可能で固有の価値の所有権を証明する技術で、その取引にはイーサリアムなどの仮想通貨が不可欠です。
購入時には、ブロックチェーン技術により、購入者から販売者へ自動的に仮想通貨が送金される仕組みとなっており、アート作品の収集や投資、ゲーム内アイテム、会員権など、多様な用途で仮想通貨による決済が活用されています。
ブロックチェーンゲーム

仮想通貨の新たな活用方法としては、ブロックチェーンゲームもあります。これは、仮想通貨やNFTの技術を活用したゲームで、従来のゲームとは異なり、実際の経済価値と直結しています。
STEPNやAxie Infinityなどの代表的なブロックチェーンゲームでは、「Play to Earn(遊んで稼ぐ)」というシステムを採用。ユーザーはゲームプレイを通じて仮想通貨を獲得し、法定通貨への換金が可能です。また、ゲーム内で入手したNFTアイテムは、売買による収益化も実現できます。
ブロックチェーンゲームは、仮想通貨を実践的に活用できるプラットフォームとして機能。エンターテインメントと投資を融合させた新しい仮想通貨の活用方法として、世界中で注目を集めています。
仮想通貨の応用

仮想通貨は、単なるデジタル通貨としての役割を超えて、金融システムの革新的な変革をもたらしています。
ここでは、仮想通貨がもたらす新しい可能性と、それを支える技術について詳しく解説します。
DeFi(分散型金融)

DeFi(分散型金融)とは、ブロックチェーン上に構築された非中央集権型の金融エコシステムです。従来の銀行等が担っていた貸付・投資・通貨発行などの金融サービスを、中央管理者なしで実現します。
高い透明性や地理的制限の排除などのメリットがある一方、スマートコントラクトのリスクも存在します。
DAO(分散型自律組織)

DAO(分散型自律組織)は、ブロックチェーン上のスマートコントラクトによって運営される自律分散型組織です。トークン保有者による投票で意思決定を行い、従来の組織と異なり、参加者全員が価値創造の恩恵を受けられます。
透明性が高く、インセンティブ設計に優れている一方で、意思決定の遅さやセキュリティリスクなどの課題も抱えています。
マイニング

マイニングとは、PCなどのコンピューターを使ってブロックチェーン上の取引記録を検証することで報酬として仮想通貨を獲得する仕組みです。
この仕組みにより、世界中に分散されたネットワークで取引データを安全に保管し、改ざんを防ぐことができます。
ビットコインのマイニング報酬は2025年2月時点で3.725BTCですが、約4年ごとに半減期があり、2028年には1.8625BTCに減少する予定です。
プルーフ・オブ・ステーク(PoS)

プルーフ・オブ・ステーク(PoS)は、保有する資産量に応じてブロックチェーンの承認権が得られる仕組みで、従来のプルーフ・オブ・ワーク(PoW)と比べて消費電力が少なく、処理速度が速いという利点があります。
イーサリアムは2021年にPoWからPoSへの完全移行を予定しており、これによりスケーラビリティの問題解決や51%攻撃への耐性強化が期待されています。
PoSシステムでは、参加者が資産を「ステーク(掛け金)」として預け入れることで、その量に応じた報酬を得ることができ、株式会社における株式保有に似た仕組みとなっています。
仮想通貨の最新トレンド

仮想通貨の技術革新の速度はすさまじく、日々新たな技術が実装されていっています。
ここでは仮想通貨の最新のトレンドの内容を紹介していきます。
ステーブルコイン

ステーブルコインは法定通貨(主に米ドル)と連動して価格変動を抑えた仮想通貨で、2024年には市場規模が1900億ドル(約27兆円)と過去最高を記録しています。
主にUSDTやUSDCなどの法定通貨担保型が広く普及しており、仮想通貨取引、国際送金、DeFi(分散型金融)での利用など様々なユースケースがあります。
日本では2023年6月の改正資金決済法によってステーブルコインが「電子決済手段」として定義され、既存のJPYCやGYENに加え、銀行や資金移動業者による新たな取り組みが進められています。
CBDC(中央銀行デジタル通貨)
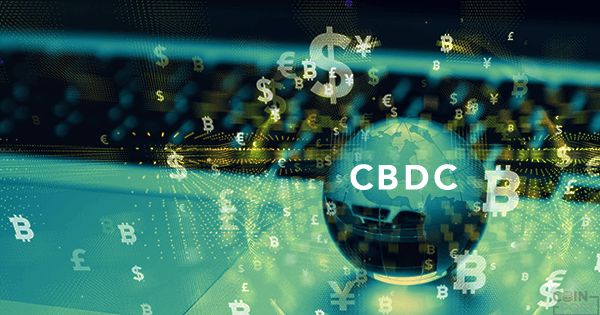
中央銀行デジタル通貨(CBDC:Central Bank Digital Currency)、通称「デジタル円」の取り組みが2023年春からスタートしており、60社を集めた実証実験フェーズに入っています。
CBDCには主に、買い物などに使用する「リテールCBDC」と金融機関間取引用の「ホールセールCBDC」の2種類があり、日本銀行のプロジェクトは前者に焦点を当てています。
CBDCの導入により、異なる銀行間での相互運用が可能になり、決済システムの効率化が期待される一方で、プライバシーの保護や自由な取引の確保といった課題も検討されています。
Web3の世界

Web3は、ブロックチェーン技術を基盤とした分散型のインターネット環境です。従来の特定企業による中央集権的な管理から、ユーザー間での分散管理へと移行することで、個人がデータや資産を直接管理できるようになります。
この変化により、データやサービスの管理がユーザー間で分散され、プライバシーとセキュリティが強化されるとともに、DApps、DAO、NFT、DeFiなどの新しいサービスや組織形態が可能になっています。
記事の監修
本記事は企業の出資による記事広告やアフィリエイト広告を含みます。CoinPostは掲載内容や製品の品質や性能を保証するものではありません。サービス利用やお問い合わせは、直接サービス提供会社へご連絡ください。CoinPostは、本記事の内容やそれを参考にした行動による損害や損失について、直接的・間接的な責任を負いません。ユーザーの皆さまが本稿に関連した行動をとる際には、ご自身で調査し、自己責任で行ってください。



 はじめての仮想通貨
はじめての仮想通貨 TOP
TOP 新着一覧
新着一覧 チャート
チャート 学習
学習 WebX
WebX

















