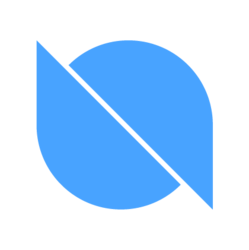アルトコインプロジェクト情報(日本語要約)
05/29 土曜日
22:22
「Mina Community Spotlight」について
2021年6月25日に開催予定のバーチャルイベント「Mina Community Spotlight」に参加することで、エコシステム、コミュニティツール、助成金プログラムなどについて学ぶことができる。
[出典元]
Mina Protocol
05/28 金曜日
23:19
CoFiX V2アップグレードとマイニング開始に関するお知らせ
2021年5月28日、NEST ProtocolはCoFiXのアップグレードとマイニング開始を発表。アップグレードにより、マーケットメイキングリスクがコントロールされ計算可能となり、コンピューティブル・ファイナンスをより実践的なものにしLPのリスクを減らすことができる。
[出典元]
NEST Protocol
13:13
MetaMaskが利用可能へ
2021年5月28日、MetaMaskがTomoFinanceで利用可能となったことを発表。当記事では、スクリーンショットに従うことでスムーズに利用ができる。
[出典元]
Tomo Finance
05/27 木曜日



 はじめての仮想通貨
はじめての仮想通貨 TOP
TOP 新着一覧
新着一覧 チャート
チャート 取引所
取引所 WebX
WebX