
10年ぶりに日銀の総裁が交代しました。日銀の政策によって株価や為替、経済状況に少なからず影響があります。投資家にとって、この交代が市場環境・経済状況へどのような影響を与えるのか気になるところでしょう。
また、日銀は金融政策の運営にまつわる事項を審議・決定する金融政策決定会合を年8回開催しています。そこで決まる金融市場調査方針や基準割引率、基準貸付利率および預金準備率などは、金融市場に大きな影響を及ぼすため、非常に重要です。
本記事では日銀が市場に与える影響や黒田前総裁が実施した政策、植田新総裁就任後の政策状況について解説します。
1. 10年ぶりの日銀総裁交代

はじめに、10年ぶりに行われた日銀の総裁交代について説明します。
1-1. 2023年4月9日より植田和男氏が就任
日銀の総裁は2023年4月9日より、黒田東彦氏から植田和男氏へ交代しました。黒田前総裁は、2013年3月20日から2023年4月8日までの10年間日銀の総裁を務めています。日銀総裁の任期は5年であるため、黒田氏は2期に渡り総裁を務め、歴代総裁では最長。
植田新総裁は、就任後初の会見で「金融緩和を維持する」姿勢を示しています。黒田前総裁が行った主な政策は「2%の物価安定の目標」や、「長短金利操作付き量的・質的金融緩和(YCC)」などです。これらの政策について、詳しくは本記事の後半で解説します。
1-2. 新総裁植田和男氏の経歴
植田新総裁は、戦後初となる学者の経歴を持つ総裁です。マクロ経済学や金融論の分野において日本を代表する経済学者で、1974年に東京大学理学部を卒業後、経済学部に学士入学した経歴を持っています。
その後、アメリカのマサチューセッツ工科大学の大学院に入学し、Ph.D.(博士号)を取得しました。カナダのブリティッシュコロンビア大学の助教授、大阪大学、東京大学の助教授を経て、1993年には東京大学経済学部の教授となりました。
また1998年から2005年まで、年8回行われる「金融政策決定会合」に参加し金融政策に関する事項の決定を行う「日本銀行政策委員会審議委員」を務めた経歴もあります。
このように、植田新総裁は総裁になる以前から、日本経済や金融市場、日銀と深くかかわってきた人物である事が分かります。
2. 日銀総裁・日本銀行が市場へ与える影響

植田新総裁の経歴について紹介しました。ここからは日銀総裁・日本銀行が市場へ与える影響について解説します。
2-1. 日銀総裁・日本銀行の役割
日本銀行には、大きく「発券銀行」「銀行の銀行」「政府の銀行」の3つの役割があります。
「発券銀行」の役割は紙幣の発行です。発券銀行が独占的に発行することによって「紙幣の安定供給」「紙幣の価値の安定」「紙幣が汚損した場合の廃棄」などを行います。
「銀行の銀行」の役割は、民間銀行からの預金受け入れや、資金の貸し出しなど。民間銀行は日銀に預金口座を開設しており、この預金口座を利用し「銀行にとっての銀行」としての役割を果たします。また、銀行同士の決済を仲介する機能も持ちます。
「政府の銀行」としては、日本銀行法や会計法などに基づき、国税などで受け入れた政府資金の管理が主な役割です。具体的には年金や公共事業費などの支払い、国税や社会保険料などの受け入れを行っています。
日本の中央銀行にあたる日本銀行の3つの役割を紹介しましたが、最も重要な役割は「物価の安定」や「経済の健全な発展」を支えることです。日本銀行の政策によっては、為替や株式市場に大きな影響を及ぼす可能性があります。
2-2. 日本銀行が経済・投資市場に与える影響
日本銀行は政策金利による利上げ・利下げを行い、経済を安定させています。利上げの目的は過熱した景気を落ち着かせ、利下げは停滞した経済の引き上げです。
利下げが起こると低い金利で融資を受けられるため、金融市場が活発化します。企業は低い金利で融資を受けられるため、設備投資や従業員への給料増加などを実施しやすくなります。個人ではローンを組みやすくなり、住宅や車の購入など大きな支出が増える傾向にあり経済の循環を促進できるのです。
反対に利上げが行われると金利が上がるため、企業や個人は資金を借りにくい状況に。ローンが組みにくくなり、住宅や車など大きな消費に回す人が減る傾向があります。よって経済活動が抑制され、過熱した景気を抑えられる効果が期待できるのです。
なお、株式市場と金利の上下は反比例の関係にあるとされます。つまり、金利が下がると株価は上がり、金利が上がると株価は下がる傾向が認められるのです。そのため投資家は、日本銀行が利上げ・利下げどちらの金融政策を行うのか注目する必要があります。
3. 黒田日銀前総裁の政策を振り返る
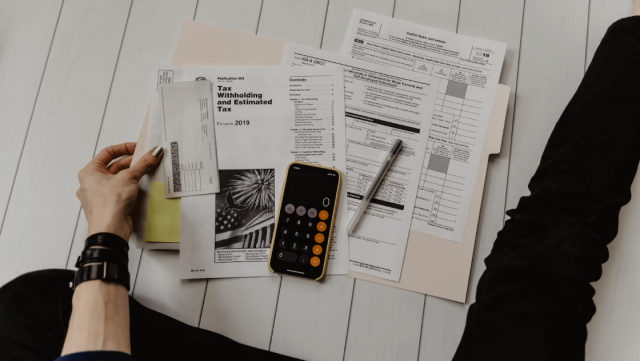
続いては、黒田前総裁が赴任してから任期を終えるまでの期間、どういった施策を行い、どのような結果が出たか紹介していきます。
3-1. 2%の「物価安定の目標」
日銀は2013年1月、「物価安定の目標」を消費者物価指数の前年比上昇率2%と定めました。黒田前総裁は2013年3月の就任直後に、この目標の達成を2年程度で達成すると宣言しました。
この目標を掲げた理由として、当時の日本は物価の下落による経済状況の縮小に陥る可能性があったことが挙げられます。デフレのスパイラルを止めるべく、物価上昇が必要だと考えられていました。
なお、黒田前総裁就任後の消費者物価指数は、-1%~4%程度を推移しています。
2023年4月に公表された総務省統計局のデータによると、2022年度の消費者物価指数は前年度比上昇率が3.2%という結果でした。上昇の原因としては、資源価格の高騰と円安による影響を受けたことが大きいと考えられています。
3-2.量的・質的金融緩和
量的・質的金融緩和は、2013年4月に金融緩和の強化策として導入されました。これは実質金利低下の効果により経済・物価の好転を目指す施策です。
量的緩和とは、操作する対象を金利から資金供給量(マネタリーベース)へ変更して、市場における紙幣の供給量を増加させることです。質的緩和とは、長期国債の買い入れや上場投資信託(ETF)の保有額を増大させることを通じて、間接的に市場に影響を与えることを意味します。
また、黒田総裁は追って2016年1月に「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」を導入しました。マイナス金利とは、民間銀行が日銀に預けている預金の金利をマイナスにすることを指します。マイナス金利とは、預金者側の民間銀行が金利を支払うという意味です。利息負担が減るため資金を借りやすくなる一方、預貯金金利の低下を引き起こして利息収入の低下を招く場合もあります。
3-3. 長短金利操作付き量的・質的金融緩和(YCC)
また、2016年9月には長短金利操作付き量的・質的金融緩和(イールドカーブ・コントロール:YCC)が導入されました。YCCでは長期金利に目標を設定し、目標達成に必要な分の国債の売買をおこないます。
YCCの効果は、日銀が2021年3月に発表した「より効果的で持続的な金融緩和を実施していくための点検」にて分析されています。点検によると、10年国債の利回りはYCCの導入と導入されなかった場合を比較すると約1%低下したという推計結果が発表されました。
ただし、この結果は一部で、人為的に国債利回りに歪みを生じさせたという見解もあります。本来、国債の利回りは市場によって決定されるべきであり、中央銀行が長期的に介入することは好ましくないという意見もあるのが事実です。
また黒田前総裁が任期終了間近だった2022年12月の金融政策決定会合では、10年国債利回りの変動幅を従来の「±0.25%程度」から「±0.5%程度」へと拡大することを決めました。しかし変動幅を拡大後もイールドカーブの問題点は解消せず、植田新総裁の今後の動向に注目が集まっています。
黒田総裁の政策を総括すると、10年間にわたって金融緩和を続けた結果として、政府債務膨張や日銀の財務悪化が進みました。近年の円安に拍車がかかる状況はその影響ともいわれ、さらにエネルギー価格高騰などのあおりを受けてインフレが加速しています。
4. 植田総裁就任後の政策状況

続いては、植田新総裁下での日銀の政策状況を紹介します。
4-1. 植田新総裁によって発表された方針
以上のような結果を受けて市場は、金融市場を知り尽くす植田総裁が就任した意味について、現在の日本金融市場が抱える問題を解決に導き、政策を変更するためであると受け取り、新総裁の緒戦に注目していました。
しかし、2023年4月・6月の金融政策決定会合でも植田総裁による政策変更は見られず、当面の金融緩和の継続、2%の物価安定目標の実現を目指す方針を表明。3回目となる7月の決定会合で一部の修正を行いましたが、微修正に留まっています。
4-2. 植田新総裁の政策による今後の影響
植田新総裁の政策によって、即座に大きな変化が起きることは考えにくいと予想されています。理由として黒田前総裁のこれまで積み上げてきた問題をそのまま引き継いだ形なため、現状の問題解決に力を入れることでしょう。
なお、植田新総裁の最初の会合では金融緩和継続という政策発表により、外貨市場では円安に振れました。これは市場から、1年以上の間にわたって政策の見直しが行われないと受け取られた事が原因といわれています。
今後の政策では物価目標の柔軟化を図ったうえで、金融緩和の枠組み見直しに取り組むだろうとされています。これには賃金上昇が欠かせないといわれており、今後の賃金上昇率に注目しましょう。
5. 植田総裁の政策変更に注目が集まる
10年ぶりに総裁の交代が行われた日銀。植田新総裁は戦後初の学者出身の総裁であり、日本を代表する経済学者ということもあり、動向に注目が集まりました。
金融市場からは政策変更が期待されていたものの、当面は金融緩和の継続、2%の物価安定目標の実現を目指して政策を行うと予想されています。
現状の金融市場が抱える問題の早期解決に努め、その後どのような政策を講じていくか、その手腕に注目です。



 はじめての仮想通貨
はじめての仮想通貨 TOP
TOP 新着一覧
新着一覧 チャート
チャート 取引所
取引所 WebX
WebX






























































