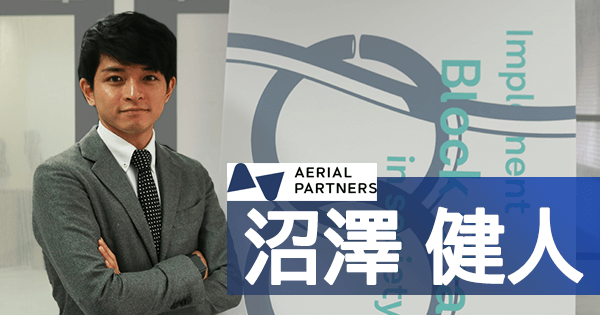
- 株式会社Aerial Partners代表取締役沼澤健人氏インタビュー
- CoinPostが株式会社Aerial Partners代表取締役沼澤健人氏インタビュー。
・仮想通貨税制の現状及び今後の課題
・少額決済に対する法整備と資産を安全に移す方法
・ブロックチェーンがエンドユーザーにもたらすこと
について伺った。
「Aerial Partners」について
-
-御社の事業内容を教えてください
-
沼澤健人 氏
弊社で提供しているサービスは、Guardian(ガーディアン)とGtax(ジータックス)の二つがあります。
前者のガーディアンですが、これは昨年から提供しているサービスで、仮想通貨の一般投資家の方と仮想通貨に精通した税理士をご紹介するサービスになっております。
基本的に仮想通貨の損益計算は非常に難しいので、そこを解消するために提供しているサービスです。
一般の投資家の方から取引の履歴等をお預かりして確定申告までフルでサポートさせていただいています。
2点目のGtaxというサービス自体が昨年の確定申告期からβテストをやっていたテック領域のサービスとなっています。
先日税理士向けの有料版の提供もスタートしたばかりですけれども、 こちらは一般の投資家、あるいは企業のクリプトのユーザーが仮想通貨取引を行なっていく中で、損益を自動で計算するクラウドツールになっています。
最後に我々会社単体でやっている活動ではないですが、一般社団法人日本仮想通貨税務協会(JCTA)というバックオフィスのサポートを提供している企業が中心となって作った業界団体でして、今複雑な仮想通貨の税務に関して、まだまだ一般の投資家だけではなく、それを支える税理士の情報源がないというのが現状なので、去年の12月からスタートして、全国の税理士を啓蒙するような活動を行う団体となっています。
こちらで「ナカモトサトシって誰ですか」というようなイロハの部分から、実際に我々が確定申告の現場で実務を築き上げているので、そういうところの情報共有をして啓蒙をすると。
あるいは実際に制度改正が騒がれてすごく良い傾向だなと思っていますが、そういったところに実務側から現場の状況を共有していくようなロビー活動も行なっています。
-この事業を始めようと思ったきっかけは何ですか
-
自分自身が困ったから、というのがきっかけです。
私自身このブロックチェーン分野に興味を持って動き始めたのが、ちょうどマウントゴックスの破綻があったその直後ぐらいのタイミングだったのですが、それ以来自身としても、仮想通貨に投資をしてみたりとか、このサービスを始める前に交換業者の金融庁登録のサポートや、ブロックチェーン領域でイノベーションを起こそうとしているプレイヤーを支援する立場にいたんですけれども、そもそも自分の確定申告どうするんだというところをきっかけに、これから新しい技術が浸透していく過程でいろいろ摩擦が起きてくるわけですけれども、この制度的な摩擦はまずいなと。
こういう制度の摩擦や税金の問題は、語弊があるかもしれませんが、本質ではない問題だと思います。
新しい技術が社会に浸透する過程で、制度的な摩擦が起きるのは世の常ですが、この領域においても、イノベーターや、仮想通貨やブロックチェーンを利用するエンドユーザーの妨げになるような状況は防がなければいけないことだと思っています。
であれば、私自身も専門家としてのバックグランドがあるので、その知見とテック面の知見を生かして、制度的な摩擦を取り除くことを通じて間接的にブロックチェーン技術をサポートしていきたいと思い、エアリアルパートナーズという会社を創業して今に至っています。
-今は従業員数は何名ですか
-
今役員従業員が14名で、そこに外部のパートナーを含めて総勢25名ぐらいのチームで事業活動をしています。
-
大前提としては新しい経済取引が生まれるスピードの方が、レギュレーションが整備されるスピードよりも圧倒的に早いというのはブロックチェーン業界に限った話ではありません。一般の方に広く普及したという意味では、去年仮想通貨元年といわれていましたが、当然その当時は、仮想通貨取引に関する細かい税制の整備ができていないという状況でした。
一般の方の色々な憶測が飛び交っていまして、「こんな形で税金を払わなければいけないのではないか」「これなら税金はかからないのではないか」などの議論がされていたのが、去年の3月から秋頃までの状況です。
僕自身も1ツイッタラーとしてその状況を見ていて、「これはまずいな」ということでツイッター上で「税法の基本原則からすればこうなりますよ」と啓蒙活動をしていたのが去年の秋口ぐらいまで。
去年の秋にタックスアンサーといって、国税庁から出る税務の個別論点の解説みたいなものが一つ出て、そのタックスアンサーがビットコインの使用に関するざっくりとした内容で、それが色々な憶測を呼び混乱していたんですよ。
「使用ってなんだろう」みたいな。
去年の夏にはすでに、仮想通貨投資家200万人時代が来ていたので、さすがに影響が大きいということで、12月1日に国税庁から所得税の仮想通貨税務に関するガイドラインみたいなものが出まして、そこで一般の投資家の方の仮想通貨の税務に関する基本的な考え方が示されたという形になります。
そこから一気に確定申告をしなくてはならないという動きが出てきました。初年度なので、何とか乗り切ったというのが、去年の確定申告期の状況です。
当然我々からすると、国税庁から出ているQ&Aの内容は、基本的には税法の基本原則に基づいた既存のフレームワークの中でのあるべき処理を解説しているもので、今我々が従っているルールは基本的には「仮想通貨だからこう」ということではなく、税法の基本原則からするとこう考えられますよね、というものなんですね。
当然そこだけでは足りていないのが事実で、Q&Aで公開されているアンサーも9個なんですけれども、仮想通貨取引が取引所マイニングとかエアドロップとか日々新しく日進月歩で進歩していく中で、ルールの整備が追いついていないというのが足元の状況です。
今税制改正が騒がれていますけれども、去年あくまでも我々の感覚値ベースで要確定申告者のなかで、きちっと確定申告ができている方ってどれくらいいるかというと、部分的にしかいないと思っています。
それが悪意に基づいた無申告であるならば然るべきペナルティーが科せられるべきですが、どちらかというと我々から見ている景色からいえば、ルールがわからないとか、頼りにできる税理士がいないとか、そういったところから来ている部分があり、それであれば申告したくてもできないという人を救っていく仕組みが必要なので、我々が提供するサービスがあったりだとか、税制自体を簡素化して申告しやすいようにしていこうというのが制度面の今の動きになっています。
-今年に入って政府からどのような施策があるのか、そして今後どう変わっていくと思いますか
-
現状当局側から出ている新しい施策というのはまだないのが現状で、当然検討されている段階なのでどう着地するのか誰も読めないというのがあります。
さきほど言っていた仮想通貨の自動計算の仕組みとかもそうですが、我々が強く願っているのは実務とか仮想通貨・ブロックチェーンの現場で起きていることを総合的にきちっと斟酌した上で制度設計をしていただきたいなと思っているんですね。
また一つ損益計算といっても、非常に難しい点がいくつもあります。
例えば、今国内だと仮想通貨交換業者の登録制度があるので16社以外は取引ができないという建てつけになっていますが、実際仮想通貨の投資家の多くが海外の取引所やウォレットサービス、クラウドマイニングのサービス、STOのプラットフォームなど国内の仮想通貨交換業社以外のところで、多くクリプトとのタッチポイントがあるわけなんですよね。
これを度外視して損益計算をするのは、計算の仕組み上不可能なことなんですよね。 なので、そういったところを斟酌した上での制度設計をしてほしいなと。
また同時に取引所から損益計算のレポートを出させる動きもあるんですけれども、去年我々のクライアントで一人当たりが使っている取引所の平均が6取引所ありまして、多くの取引所を使っているお客様の取引を一取引所ごとに切り分けて損益を計算するってことがそもそも出来ないんですよね。取得原価がわからないので。
なので、そういった根本的な現場で起きていることと、制度設計で今審議されている内容に若干の乖離を感じていて、我々としても何ができるかというと実務の現場の状況を共有していく立場として、そういった設計制度の部分にも関わっていきたいのというふうに思っているんですね。
私が研究員の一人として入っている、暗号通貨に関する租税制度に関する研究会というのがありまして、これが今年の4月に政策提言をさせていただいているんですね。
その内容は後ほど改めて共有させていただくんですけれども、仮想通貨の少額決済に関する特例であったりですとか、クリプトToクリプトの取引に関する非課税であったりとか、そういったところを盛り込んで提言させていただいているんですけれども、そこからさらに実際に実務の現場で起きている色々な新しい取引が生まれて、新たな課題というのも当時からすでに出て来てしまっているので、そこをさらにアップデートしていくためにも政策の制度設計の部分に実務の現場から関わっていけたらなという思いで活動しています。
-
基本的には仮想通貨の投資家の方って投資とか確定申告とかを初めて経験している方が多くて、質問の中でもベーシックなものが多いですね。まだまだ啓蒙ができていない状況です。
例えば、単価の計算方法で移動平均法と総平均法というのが選択適応できるような状況となっているんですけれども、そんな言葉を一般の方は聞いたこともないので、それに関するご質問はよくいただきます。
他には「仮想通貨、秘密鍵を紛失しました」とか、「利用していた取引所が突然閉鎖になりアクセスできない」などは日常的に寄せられる質問の一つでもありますし、これら確定申告の際に、取引していた履歴データ自体が手元にないという形になるので、こういったときにどうしたらいいかといった質問は非常に多いです。
なので我々がこの領域で専門でさせて頂いている中で、実務を通して感じるのは、まだまだ一般の投資家の方の仮想通貨に関するお話ですとか、仮想通貨の税に関するリテラシーはそこまで高くないというのが現状で、我々も啓蒙をもっとやっていきたいと思っています。
-
我々が創業当初から掲げているビジョンは、ブロックチェーンを本当の意味で社会実装するということで、ずっとそこを目標に事業活動を行なっています。
事業領域としては仮想通貨の税務や、損益計算のサポートしている会社だと外からは捉えられることが多くて、それ自体はまったくその通りですが、我々がよく言っているのが新しい技術が浸透する過程で起きる摩擦って大体「制度・技術・体験」だと言っていまして、これはブロックチェーン技術に関しても然りです。
今まさに税制とか、証券法周りの規制関連の制度的な摩擦が最初に浮き上がってきて、その後に色々な技術的な摩擦であったりとか、最終的にはユーザーが使うことを選択出来るに至る体験的な摩擦を解消しましょう、というのが我々の事業のアプローチです。
広くブロックチェーン技術を使ったユーザーの取引や、仮想通貨取引を支援していくというのが我々の事業領域なので、税務にかかわらず、トレードや資産管理、特に仮想通貨の資産管理全般など実際に投資家の方が摩擦に感じる部分を解消したいなと思います。
仮想通貨の資産管理全般というのは、例えばある家族がいて、その一家の主人が不慮の事故で何か起きた場合に、どうやって彼が持っている仮想通貨資産を安全に引き継ぐかということです。
それは秘密鍵の分散管理をどうするかという技術的な問題ももちろんありますが、それ以前にどこの取引所を利用していて、どういったウォレットを使っているかなど、彼の資産がどこにあるか管理する手段って今はないんですよ。
これはまだ浮き彫りになってきていない一つの課題ではあるけれども、個人の仮想通貨を安全に管理して大切な人に安全に引き継ぐ方法は我々の研究領域の一つで、実は創業した時から次に来る新しい摩擦の一つだと思っていて研究開発をやっているというのはあります。
これは全体像というか、遠い未来の話です。
近い未来の話をさせていただきますと、Gincoさんのプレスも然りですし、freeeさんとのリリースも然りですが、まずは安心安全に仮想通貨取引ができるインフラを作っていきたいというのが直近の目標で、かつ、損益の計算や税金の計算といったところに、皆さんの有益な時間を使っていただきたくないので、我々はどういった取引所で仮想通貨取引をしていても、どのウォレットを使っていても、どの事業者のクラウドマイニングを使っていても、どんなSTOに参加していても、最終的には自動的に損益が計算されていて、確定申告書類が自動でアウトプットできる世界を作っていきたい。
要はインフラの中でも、取引所とかマイニング事業者などのゲートウェイとか、ウォレットサービスとかがフロントのインフラ技術だとしたら、我々それをもう一つ下のレイヤーで支えていくようなインフラを作っていきたいと思っていまして、それを作りながら安心安全に取引でき、また当局側もそれによって全力で支援ができる環境が整うと思っています。
皆さんは、税金というと払う行為なのでどこかネガティブなイメージもありますし、私自身も若い頃はそういうふうに考えていたんですけれども、ルールの設計者としても、脱税の恐れがあったりだとか、マネーロンダリングの恐れがあったりだとか、そういった状況下で全力で応援していくことは現実的に難しいです。
であれば、我々が当局側もきちっと環境整備できる前提のインフラを作って、当局の協力も仰ぎながら仮想通貨取引がもっと浸透して、ひいてはブロックチェーン技術が社会実装できるような世界が近い将来きたら嬉しいなと思っています。
-
少額決済の部分に関しては、例えば法人税法で償却性資産を減価償却計算せずに、少額であれば一括費用計上していいというルールがあり、少額であれば大丈夫というケースが複数ありまして、基本的にはそこに倣って進めていくんだろうなと思っているんですけれども、年間で一定の上限を求めて、そのペイメントにかかる税金に関しては計算の対象に含めなくていいですよ、所得を0にしていいですよということは考えられます。
作るルール自体はシンプルですけど、仮想通貨というのは投資対象でもあり、かつ支払い手段でもあるという他の金融製品にない性質を持っていまして、例えばゴールドで我々はスターバックスのコーヒーやビックカメラの家電は買いませんよね。
株式でも買いませんし、外国為替ドルでも買いませんよね。
というように、すごく特殊な性質を持っていてペイメントのところの税金をかけませんというふうにしたとしても、投資商品としてみた仮想通貨の損益計算と密接に絡まっているので、実は少額決済を課税しないとしても、実際の損益計算の実務のところって、例えば決済にしか仮想通貨を使ってない人であれば関係ないですけど、決済もトレードもする方を想定すると、ルールの設計次第では損益計算の実務自体が実は逆に複雑化してしまう可能性もあります。
トレードで計算している計算基礎の中に、ペイメントで払ったやつを、履歴としては送付先のビットコインアドレスに送金した記録だけが残っていて、これをペイメントなのか、純粋な自分のウォレットから取引所への送金なのかといったところを判別して、かつ支払いに関するところ、上限いくらまでは計算に含めないっていうのを全体の計算のなかでやっていかないといけないので、安易に簡略化をしようとすると逆に損益計算が複雑になってしまうこともあるんです。
なので我々はそういったところを、実際に投資家の方を相手にしているチームなので、こう変えた場合にこういった弊害がありますとかそういったところの情報共有はどんどんやっていきたいなと思っています。
逆に実務の現場が混乱しないような、制度設計をしてたいただければと思います。
後半の資産管理の話でいくと、非常に面白いテーマだと思っていて、 私も仮想通貨の取引歴が長いので、自分の身にもしも何かあると考えると、本当に八方塞がりで何も解決手段がないというのが現状です。
取引所に関するカストディアンというのが盛り上がっていますけれでも、一般の個人投資家の方が複数の取引所を利用して複数のウォレットを使っている中で、そこを安全に引き継げる仕組みは現状ないです。
難しいのが、社会課題として浮き彫りになってくるのが、実際に仮想通貨の投資家の方が亡くなってしまって仮想通貨資産がこの世から消えてしまう、というようなことが出てくると、また税金の問題と一緒で一つの摩擦として課題が浮き上がってくるというところなので、我々もどのタイミングで投資をしていくかというのはかなり難しいところではあるんですけれども、段階としては基本的には二段階だと思っています。
仮想通貨資産を安全に管理する資産情報のお預かりに関しては、基本的にはトラストに基づいたビッグプレイヤーの登場があって我々の仮想通貨資産に関する情報を保険料を払いながら、預かっておいてもらって、なにか相続などのタイミングで適切に引き継ぐというのが現実的だと思っています。
初期はトラストに基づかないと成り立たないと思っているので、その先の未来で我々が見出しているのは分散的な管理をしていくということでして、個人情報の中でも最も大切な情報の一つである資産の状況というのをビッグプレイヤーのトラストに基づかない形で管理する方法はないでしょうかと。
その前段階で、マルチシグネチャの技術に関する管理であったりとか秘密鍵の分割に関しての研究開発などを行なっています。
なので我々が最終的に目指していくところは、個人が他者に寄らずに自分の責任で資産を管理しつつ、自分の信頼のできる大切な人には安全に資産を引き継げる仕組みは必要かなというふうに思っています。
これは一例でして、我々は仮想通貨の取引支援事業というふうに言っていますが、今浮き彫りになっている課題って税金の部分であったりだとか、今後仮想通貨の資産管理の部分がでてくるのは確実なんですが、そのほかにも、ブロックチェーンの技術の根本思想自体が分散化なので今までの既存のフレームワークでは捉えられない新しい経済事象とか信頼の作り方とか価値の味方っていうのが出てくる中で、僕たちが想像もできないような考え方が必ず出てきます。
我々はそういった未知の課題をいち早く識別して、実際に仮想通貨・ブロックチェーンを使うユーザーが困る一歩手前で摩擦を解消して、ひいてはブロックチェーン技術を社会実装していくというアプローチで事業をやっています。
-
前回FinSumのときにGincoの森川さんが話していた内容で、例えばシェアリングエコノミーであれば今まで価値がつかなかった遊休資産が一つ新しい経済圏になりましたよと。
ブロックチェーン技術も浸透して社会実装された過程で、分散化された未来で考えると、我々の経済活動が全く違う信頼とか、価値の生み出す方法だとか、価値を移転する手段がでてくると思っていて、基本的には根本の分散化思想というところに惚れているというのがあります。
なので今まで社会で経済的に評価されていなかったものが評価できる仕組みができると思います。
例えばオープンソースのソフトウェアって非常に分かりやすいと思っていてLinuxのようなソフトウェアがあれだけ経済的にも間接的にインパクトを与えているけれども、初期のLinuxの開発者たちが経済的な価値を引き換えに得られているかというと実はそうではないです。
今はそこに対して、価値がついて経済になるという仕組みがないんですけれども、いわば公共財に対して経済的な活動が生まれるかというと今はそういうインフラがないという中でICOにしてもSTOにしても、価値があると分かっているけれども、経済的な価値を引き換えることができなかったような活動がきちっと経済として成り立っていくような未来があるんじゃないかなと思います。
どんどん組織に従属していくという概念が薄れていく中で、個々人にボートのオールが渡されて個々人で自分の名前で生計を立てていくという人がどんどん増えていく中で、経済的な価値として評価されなかった部分が評価されるような未来があるかもしれない。
新しい経済活動が生まれてくるのではないか。
実際それがどういった形になるか分からない社会実験のフェーズなんですけれども、その新しい歴史が塗り替わる瞬間みたいな部分に、僕は当事者として関わっていたいという思いがすごく強いです。新しいブロックチェーン革命で価値に革命が起きている状況の中で、今やっている事業は地味で目立ち辛いところではあるんですけれども、価値そのものが変わってしまうかもしれないという時代の幕開けに携わっていたいということで事業活動をしています。
その変化を妨げるような税の問題であったりだとか、マネーロンダリングの問題であったりだとか、資産管理の問題ですとか、本質的ではないですが重要なことっていうのが大きな摩擦になってしまっているので、我々はそこを解消したい。
それによって間接的にブロックチェーンが社会実装することを手伝っていきましょうというイメージでいます。

撮影:中村晋
税制の現状及び今後の課題
-今の税制の流れを簡単に解説していただけますかユーザーからの質問
-ユーザーからよく尋ねられる質問は何ですか
撮影:中村晋
「Aerial Partners」の将来について
–エアリアルパートナーズが将来取り組みたいことや、将来の展望をお聞かせください少額決済に対する法整備は?資産を安全に移す方法は?
-少額決済についてどのように法整備をするべきだとお考えですか。また、家族などに資産を安全に移す方法として現時点でどのようなアイデアがありますか
撮影:中村晋
ブロックチェーンがエンドユーザーにもたらすことは?
-ブロックチェーンが社会実装されることでエンドユーザーにどのようなものがもたらされると思いますか■沼澤 健人 代表取締役
有限責任 あずさ監査法人で監査業務やM&A業務に従事した後に、2014年にアプリ開発等を手がけるスタートアップを創業。2016年から会計コンサルティング事業等を行う株式会社Atlas Accounting代表も務める。2017年に株式会社Aerial Partnersを創業。
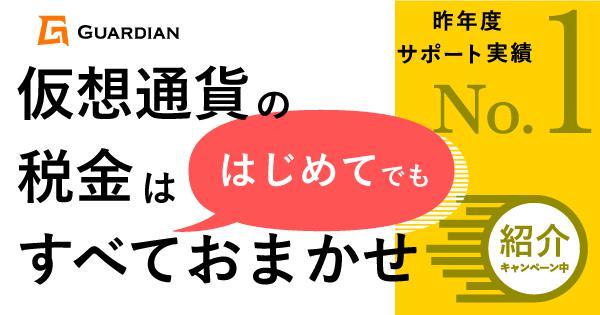



 はじめての仮想通貨
はじめての仮想通貨 TOP
TOP 新着一覧
新着一覧 チャート
チャート 取引所
取引所 WebX
WebX































































