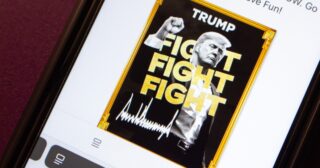日本における暗号資産の金融商品取引法への移行がいよいよ本格化しつつある。17日にはブロックチェーン推進議員連盟が、来年の通常国会での法整備を目指すことを表明し、税率20%の分離課税実現への「最終局面」に入ったとの見方もある。
金融庁による金融審議会の暗号資産制度に関するワーキング・グループでは、インサイダー取引規制や銘柄分類など、具体的な制度設計の議論が進む。
暗号資産業界にとって歴史的な転換点となる金商法移行。交換業者(取引所)運営の負担増加やイノベーション阻害への懸念も指摘される中、業界団体はどのように対応を進めるのか。
一般社団法人日本暗号資産等取引業協会(JVCEA)の代表理事を務める小田玄紀氏に話を伺った。
インタビュイー紹介

JVCEA代表理事(会長)小田玄紀氏
一般社団法人日本暗号資産等取引業協会(JVCEA)の代表理事を務めるほか、SBIホールディングス常務執行役員、株式会社ビットポイントジャパン創業者として、日本の暗号資産業界を牽引する。
金商法移行の意義
日本が暗号資産を金商法の管轄にしていくことは、国際的な流れに逆行しているとの指摘もある
日本では、暗号資産を金商法の規制対象とする一方で、「有価証券とは異なるアセットクラス」として位置づけることが明確化されています。この考え方はアメリカや諸外国と同様であり、国際的な潮流に沿ったものとなっています。
金融審議会では規制強化の議論が中心だが、イノベーションについても議論されるのか
金融審議会は「規制強化に関する議論」を行う場であり、イノベーション推進を直接議論する場ではありません。適切な規制強化を進めることで、結果的に暗号資産の社会的評価を高め、日本のイノベーションへと繋がることが期待されています。
厳しい規制がかかり、イノベーションを阻害しないかと懸念の声もある
今回の法改正では、金融庁の方に業界の実情を真摯に受け止めていただき、暗号資産の特性を理解した上で規制の枠組みを検討して頂いています。既存の金商法をそのまま適用するのではなく、暗号資産特有の性質に配慮した規制内容となる見込みです。
一部に制約が生じる可能性はありますが、規制に縛られて何もできないと考えるような人はイノベーターではありません。規制の枠組みを理解した上で、イノベーションを起こす人こそが真のイノベーターではないでしょうか。
規制強化による取引所への影響
開示規制やインサイダー規制により、日本で暗号資産を取り扱えなくなるとの懸念もある
全ての暗号資産が開示規制対象となるのではなく、開示規制の対象となる暗号資産とならない暗号資産に区分されます。分散性の高い銘柄は開示規制の対象外とされており、主にIEO銘柄や日本居住者向けに販売される暗号資産が規制対象となります。また、開示内容は有価証券のような詳細なものではなく、業界が現実的に対応可能な水準に設定される見込みです。
暗号資産交換業者の負担増はどの程度想定されるか。銘柄制限などの影響はあるか
暗号資産交換業者の経営管理態勢は、企業によって整備状況が大きく異なります。今回の法改正に伴う負担増は、非現実的な水準を求めるものではなく、金商業者として適切な経営管理態勢の構築を目指すものです。そのため、実際の負担増は各企業の現状によって大きく変わることになります。
なお、取扱銘柄が大幅に減少するような事態は想定されていません。今後、個別銘柄の取扱可否について各社が独自に判断するケースはあり得ますが、今回の金商法移行に伴う分類によって、直ちに取扱制限がかかることはないと考えられています。
取り扱い銘柄について
銘柄の分類基準と今後の影響は
大きく2つの分類に分けており、発行者(中央集権的管理者)が存在する暗号資産とそれ以外の暗号資産となっています。ビットコインやイーサリアムなどは後者に該当します。
発行者が存在する暗号資産についても、取扱いが大幅に厳格化されるわけではありません。
IEOや日本居住者向けの販売・募集を行う場合、発行者に情報提供義務が課されますが、これは現行のIEOで既に実施されている内容です。
また、日本国内で募集・販売行為を行わず、暗号資産交換業者が取扱いのみを行う場合は、交換業者に投資家への情報提供義務が課されますが、これも既存の暗号資産審査プロセスで対応している内容であり、大きな課題は生じないと見られています。
これまでやっていたことを、さらにしっかりと責任をもって対応していく、その精度をさらにあげて、投資家保護に努めるというのが今回の改正の精神となります。
個人への影響
インフルエンサーやKOL(Key Opinion Leader)などの業界発信者がインサイダー規制で発信しづらくなることは
金商法改正に伴い、広告規制はこれまで以上に厳格化されますが、求められる内容は基本的なルールの徹底です。インフルエンサーらが発行者や取引所から対価を受け取って広告を行う場合、PR表記を明示することは、暗号資産に限らず他の業界でも一般的に行われています。
広告案件であるかどうかを明確にすることは、投資家保護の観点から重要です。
国際規制との比較と協力関係
米国CLARITY法案や欧州MiCAなど、国際規制との比較をどう見るか
今回の規制については、米国やMiCAも参考にしています。日本はあくまでも日本の法律になりますが、参考にしていることは事実です。むしろ、今後日本の法的枠組みを各国が参考にしてくるところもあるかもしれません。
ICO・IEO市場の構造的課題
日本でIEOは今後も継続できるのか
IEOについては、事業者がすでに様々な取組みを行っており、従来よりも多くの情報開示を実施しています。適切な開示を行っている事業者にとっては、今回の規制変更に対応できると考えています。
なお、IEOについては従来から一定の情報開示を求めており、今回の法改正によってIEOが実施できなくなることはありません。優良なIEOプロジェクトは健全な形で成長すべきであり、むしろ積極的にチャレンジしていただきたいと考えています。
レンディングやDEX・DeFiについて
暗号資産レンディングについて、今回の法改正でどのような対応が求められるのか
レンディングについては、これまで明確な規制がありませんでしたが、今回の金商法改正に伴い、暗号資産レンディング事業者に一定の登録制度を設けるべきとの議論が行われました。
これは暗号資産レンディングを禁止するものではなく、むしろ健全な市場形成を目指すものです。暗号資産レンディング事業者は顧客から暗号資産を募集し、管理を行います。こうした業務に規制が存在しないことは不適切であり、ハッキング被害などのリスクも想定されることから、法律による適切な利用者保護を図る必要があるという判断です。
DEXやDeFiは日本では展開できないのか
DEXやDeFiについて、日本政府や当局としては明確に禁止とはしていません。DEXやDeFi市場は大きく、これから適切に評価されるべき市場であることは事実です。他方で、管理者がいないDEXは何か課題が起きた際にどう解決するのかが不明瞭となっています。この点を今後解決していく必要があると思います。
これはあくまでも私見ですが、管理責任・運用責任を明確にしたDEX・DeFiを構築していくことは、今後注目される可能性があります。ブロックチェーン技術の重要な価値の一つであるスマートコントラクトは、適切に評価されるべきです。全てを一律にDEX・DeFiとカテゴライズするのではなく、管理責任・運用責任を明確にしたスマートコントラクトサービスには、世界的な需要があると考えています。
日本発でこうしたサービスを展開できれば、大きな潮流を生み出せる可能性があるでしょう。
税制改正の展望は
分離課税への移行など、税制改正は本当に実現するのか。いつから適用されるのか
日本の所得税制度において、税制優遇が適用されるための必要条件の一つが金商法の対象となることでした。
金商法への移行は税制改正の十分条件ではありませんが、必要条件の一つであることは確かです。暗号資産に対する世界的な評価の変化、そして日本国内で口座数が1300万を超えている現状を踏まえると、暗号資産の社会的役割が変化していることは明らかです。こうした状況を含めて総合的に判断されるものと考えています。
適用時期については、今後の国会審議次第であるため確定的なことは申し上げられませんが、与党だけでなく多くの政党が前向きに検討していると認識しており、日本の経済・財政を成長させるためにもぜひ推進をして欲しいと考えております。
関連:SBIグループで資産運用|証券・銀行・仮想通貨投資を効率的に



 はじめての仮想通貨
はじめての仮想通貨 TOP
TOP 新着一覧
新着一覧 チャート
チャート 取引所
取引所 WebX
WebX