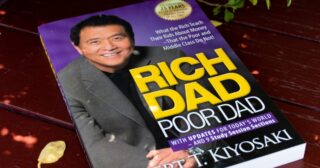ビットコイン(BTC)黎明期から暗号技術の最前線に立ち、ローンチ前にサトシ・ナカモトとやり取りをしていたことで知られるアダム・バック(Adam Back)氏。現在はブロックチェーン技術開発を牽引するBlockstream社のCEOとして、ビットコインの拡張ネットワーク「Liquid」を推進している。Liquidは高速性と秘匿性を備えたレイヤー2で、ステーブルコインやRWA(現実資産)のトークン化も可能だ。
同社は2025年2月、台湾発のWeb3ソリューション企業Echo Xとの提携を発表。アジア市場への本格展開を目指す狙いと今後の展望について聞いた。
Liquid上でのUSDT活用を促進
──Echo Xと提携を発表した背景は。Liquid上でテザー(USDT)が利用される意義について聞かせてほしい。
バック氏:EchoXと提携した大きな理由は、彼らがLiquid Networkの採用を推進してくれるからだ。彼らが市場へ持ち込んだ最初のプロジェクトの一つが、Liquid上でのUSDT導入だった。これにより、すでに5000万ドル以上がエコシステムに流入している。
Liquidには、ダスティング攻撃(極小額のコインを送りつけ、取引履歴を分析してウォレットの所有者を特定しようとする行為)などへの耐性があり、秘匿性とセキュリティを兼ね備える点がユーザーから評価されている。
特に台湾では、国際決済でUSDTの利用が広がっている。現地企業が各国サプライヤーとの取引に活用しており、銀行送金に比べ効率的だ。この動きは地域全体へ拡大しつつあり、私たちが注目する理由になっている。
RWA市場の拡大とトレジャリー企業
──今回の提携には、RWA(現実資産)のトークン化を推進する目的もあるようだが、RWA市場の成長をどう見ているのか。
バック氏:RWA市場は非常に興味深い領域だ。なぜなら、異なる資産クラスをまたぐものだから。一方には証券会社を通じて株や債券を買う世界があり、もう一方には取引所でビットコインや先物、デリバティブ、ステーブルコインを取引する世界がある。この二つを組み合わせることは従来は困難だった。

最初に起きたのは、いくつかの国でETF(上場投資信託)を通じて証券会社経由でビットコインを購入できるようになったこと。日本でもいずれそうなる可能性があるだろう。そして、次に起きているのは逆方向の流れ。つまり、株式がトークン化され、取引所で扱えるようになり始めている。
証券ライセンスを持ち、トークン化された株式を上場・取引できるプラットフォームも登場している。その最初の事例は、ビットコインを財務戦略として保有するトレジャリー企業群だ。米MicroStrategyや日本のメタプラネット、スウェーデンのH100グループ、フランスのCapital Bなどが代表例で、ビットコイナーにとって興味深い取引対象になっている。
取引所には証券会社にはない強みもあり、例えば24時間取引や低コストのレバレッジ取引、マージン取引が可能なことや永久先物の提供などだ。
──アルトコインを財務戦略に組み入れる企業も登場しているが。
バック氏:おそらく、うまくいかないだろう。ETFの買い手や年金基金、アブダビ投資庁などのソブリンファンド(政府系ファンド)といった機関投資家は、いずれもビットコインを購入している。
アルトコインでも同様にトレジャリー企業を目指す動きはあるだろうが、機関投資家は興味を持たないと思う。彼らはプロの投資家で、長期的に価値のある資産を求めているからだ。アルトコインは投機的すぎるため、投資対象にはならない。
ビットコインは唯一、初期から商品(コモディティ)として広く受け入れられたコインだ。多くのアルトコイントレーダーは、最終的にビットコインを増やすために取引しているのだと思う。ビットコインには堅牢性とセキュリティがある。そして、長期的に価値の保存手段として利用可能なのはビットコインだけだろう。
ビットコインのレイヤー2が拓く可能性
──日本では、ライトニングネットワークを含むL2ソリューションの活用や認知度はいまだ高くない。「Liquid Network」とは何か、改めて教えてほしい。
バック氏:一般的に、ライトニングネットワークは小売での支払い、つまりPOS決済で使われている。そのため、ライトニングネットワークの普及はその国のPOS技術や小売チェーンにどれだけ統合されているかに左右される。
新興国の方が小売での決済や送金が浸透しているが、日本でもビットコインのレイヤー2を広げていく機会は十分にある。その一端を担えるのがEcho Xなのだ。
──Liquid Networkの技術的な優位性は何か。
バック氏:まず、Liquidでは資産発行が可能だ。ビットコインのメインチェーン上ではビットコインしか扱えないが、LiquidならUSDTのようなステーブルコインや、ライセンスを取得した株式などの証券を発行したり取引したりすることもできる。また「SideSwap」という、非カストディ型スワップを可能にするプラットフォームもある。

さらに、最近の新しい動きとして、Liquidウォレットがライトニングにも対応し始めている。いわゆる「ノードレスライトニング」と呼ばれる仕組みで、Liquidとライトニングを統合してスワップできる点が普及を後押ししている。
具体的には、Liquidのビットコインをライトニングにスワップして支払いに使ったり、逆にライトニングをLiquidビットコインにスワップして受け取ったりできる。つまり、ウォレット自体はLiquidビットコインだけを保管しているが、ユーザーからするとライトニングウォレットを使っているのと同じ体験になるのだ。
──Blockstreamが注力する分野は。
バック氏:ビットコイン・インフラの構築だ。私たちはLiquidの主要開発者であり、Core Lightningと呼ばれるライトニングの実装も手掛けている。
その周辺を支える技術開発にも幅広く取り組んでいる。Liquidおよびビットコイン用のブロックエクスプローラ、ハードウェアウォレットやソフトウェアウォレット、Liquid上で証券を扱うための資産管理プラットフォーム「Blockstream AM」、さらに企業向けウォレットやカストディ技術などがある。
加えて、Simplicityと呼ばれるスマートコントラクト技術にも力を入れている。これはビットコイン向けの次世代スクリプトシステムで、現在はLiquid上、つまりビットコインのレイヤー2で稼働している。ただ、将来的にはビットコイン本体への実装も視野に入れており、興味深い展開につながるかもしれない。
「セキュリティ第一」を原則に
──アジア太平洋市場でのビジョンや目標は。
バック氏:Echo Xは優れたシステム統合能力を備えており、すでに地域でのビジネス関係も築いている。そうした強みを生かし、日本や香港をはじめとする現地企業に対してビットコインのレイヤー2上でのRWAトークン化やUSDT取引の支援を進めていきたい。
Liquidとビットコインはいずれも「セキュリティ第一」を原則とするプラットフォームであり、その前提を軸に展開していきたいと考えている。

BlockstreamのCEOを務めるアダム・バック氏
──WebXに参加した狙いと日本市場に期待することは。
バック氏:WebXのような場は、地域の業界関係者と一堂に会える絶好の機会だ。Blockstreamはデジタルガレージとも協力しており、会場でチームと顔を合わせることができた。
日本は米国同様、規制環境の改善が進んでおり、ビジネスにとってより開かれた市場になる可能性がある。ETFの承認や課税制度の見直しが実現すれば、市場環境はさらに整うだろう。また、円建てステーブルコインの発行が承認されたことも新たなユースケースの創出につながる可能性があり、非常にポジティブに捉えている。
|インタビュー:CoinDesk JAPAN広告制作チーム
|構成・文:橋本史郎
|撮影:多田圭佑
※当記事は、CoinDesk JAPANに掲載された広告シリーズ「Sponsored by WebX」からの転載です。
※CoinDesk JAPANを運営するN.Avenueは、CoinDeskの公式日本版やWeb3領域のカンファレンスやコミュニティ活動を行う情報サービス企業です。2023年7月より、国内最大の法人会員制Web3ビジネスコミュニティサービス「N.Avenue club」を展開。国内外のゲスト講師を招き、ナレッジ共有とディスカッションを行う月例「ラウンドテーブル」、会員企業と関連スタートアップや有識者との交流を促す年3回の「ギャザリング」等を実施しています。▶N.Avenue clubの詳細はこちら。



 はじめての仮想通貨
はじめての仮想通貨 TOP
TOP 新着一覧
新着一覧 チャート
チャート 取引所
取引所 WebX
WebX