
日本のWeb3およびFintech領域をリードするDeFimansが主催する「DeFimans Fintech & web3 Night」が開催された。
Japan Fintech Week 2025の公式パートナーイベントとして位置づけられた本イベントでは、業界最前線の企業や政府関係者が一堂に会し、多角的な議論が展開された。本レポートでは、トークセッション「DeFiとCeFiの融合と未来」、「石破茂総理が掲げる「地方創生2.0」を徹底解説!」の2つのテーマを中心にその模様をお届けする。
共催企業によるプロジェクト紹介
登壇者
- 小野暢思氏(株式会社DeFimans代表取締役/Co-CEO)
- 柳澤力也氏(BitGo Director, Sales Head of Japan)
- CJ Fong氏(GSR Managing Director, Head of Sales [APAC & EMEA])
- Dennis Bree氏(Figment Global Head of Growth)
- 佐藤太思氏(DeFimans代表取締役/Co-CEO)

イベント前半では、海外Web3企業の代表者たちが日本市場戦略とDeFi(分散型金融)・CeFi(中央集権型金融)の融合について議論を展開した。DeFimansの佐藤氏は、米国ではこの融合をグローバルで効果的に進めている動きがある点を指摘。一方で日本には米国と比較して規制環境が整備されている側面もあるという。また、今後の金融市場における技術革新と規制調和の重要性も強調した。
BitGoの柳澤氏はカストディサービスについて「暗号資産に関わる様々なサービスの裏側でソリューション提供をしている」と説明し、頻発するハッキングへの対応として「規制要件を超える高度なセキュリティ対策」の必要性を訴えた。国際展開においては各国における規制対応の重要性にも触れている。
マーケットメイカーのGSRのFong氏は「流動性確保によりプロジェクトの本質的価値を守る」ことを使命とし、投機的な市場活動の抑制を目指すと語った。健全な金融市場形成における流動性の重要性についても言及し、リスク管理と市場安定性に関する具体的な知見を共有した。
ステーキングサービスプロバイダーのFigmentのBree氏は、「単なるサービス提供を超えて業界全体を教育する」という哲学を紹介し、新興ビジネスの育成と支援を目標としていることを述べました。日本の暗号資産エコシステムの健全な発展に向けてパートナーシップを組むことへの取り組みを表明しました。
CeFiサービスは複数の収益源から安定した利回りを目指し、DeFiプロジェクトへの資金提供に力を入れる一方、DeFi側はより多様な選択肢を提供する役割を担っているという。注目すべきは「日本の金融機関がグローバルのオンチェーンに登場できる時代がくる」という発言で、伝統的金融機関とブロックチェーン技術の融合が加速する可能性が示唆された。
DeFiとCeFiの融合の現状
Web3企業と伝統的金融機関の接点が増えつつある中、DeFi(分散型金融)とCeFi(中央集権型金融)の相互作用が生み出す可能性と課題について、国内外の専門家による議論が展開された。特に日本市場特有の環境下での発展経路に焦点が当てられた。
日本市場の特異性と国際的視点
GSRのFong氏は日本の暗号資産市場が持つ二面性を指摘した。「日本は独立した経済圏としての強みを持つ一方、グローバル市場との分断が課題となっています」と述べ、海外投資家による日本市場へのアクセス制限が流動性確保の障壁になっている現状を分析した。同氏はこの状況を改善するためには、取引所や金融機関の国際的視点の拡大と、DeFiプラットフォームとの連携強化が不可欠だと強調した。
Figmentはアジアでのステーキングビジネス展開の経験から、日本市場の特殊性を実感したという。Bree氏は「シンガポールとは異なる商習慣や規制環境に適応することが最大の挑戦でした」と説明。一方で、現地パートナーとの協力体制を築くことで、規制に準拠した機関投資家向けステーキングサービスを提供できる見通しを示した。
セキュリティと流動性の確保—信頼構築への取り組み
セキュリティ面では、BitGoの柳澤氏が近年の大規模ハッキング事件を踏まえ、カストディサービスの進化について解説した。「DMMビットコインやBybitの事例が示すように、セキュリティは業界全体の信頼性に直結し、重要である」と指摘。同社は法規制の要件を満たすだけでなく、それを上回るセキュリティ対策を実装することで、機関投資家が安心して参入できる環境の構築に取り組んでいるという。
市場の安定性という観点からは、GSRが提供する流動性の重要性が強調された。「流動性はプロジェクトの命綱です」とFong氏は述べ、適切なマーケットメイキングが単に価格を安定させるだけでなく、エコシステム全体の持続可能な成長を支える基盤になると説明した。
革新的収益モデルと規制調和—融合の未来像
セッションの後半では、DeFiとCeFiの融合が進む中での今後の展望が議論された。パネリストらは、今後の発展において特に重要となる要素として以下を挙げた。
- ステーキングやリステーキングなどの革新的な収益モデルによる従来型金融とWeb3の架け橋構築
- 規制が厳格な日本市場における規制環境と調和したオンチェーン経済へのアクセス経路の確立
- 日本固有の金融環境に適した独自の統合アプローチの必要性
討論を通じて浮かび上がったのは、成熟した日本の金融市場とボーダーレスなWeb3テクノロジーの統合には独自のアプローチが必要だという認識だ。透明性と効率性を追求するDeFiの特性と、安定性と信頼性を重視するCeFiの強みを組み合わせることで、グローバル水準と日本の規制環境が調和した新たな金融エコシステムの構築が期待される。
米国Web3戦略に呼応する日本の地方創生政策
登壇者
- 谷本有香氏(Forbes JAPAN 執行役員Web編集長)
- 川崎ひでと衆議院議員(総務大臣政務官/前自民党web3PT 事務局長)

イベントのハイライトは、総務大臣政務官の川崎ひでと衆議院議員とForbes JAPANの谷本氏による対談だった。この中でトランプ大統領の「米国を地球上の暗号資産の中心地にする」という発言について、川崎衆議院議員は次の3つの目的があると分析した。
- リーダーシップ表明による、企業・資金・人材の米国への流入促進
- グローバルスタンダードが未確立な状況への対応
- 米国でのイノベーション創出による主導権確保
川崎氏は「日本も米国と歩調を合わせていく必要がある」という見解も示し、会計監査問題などのWeb3産業の課題も米国での整備進展により解決する可能性が指摘された。
さらに川崎氏は日本の政策決定プロセスを説明しつつ、政策実現には「骨太の方針」への組み込みが不可欠だと強調。現政権の特徴として「地方創生という文脈にWeb3を活かす」方針も述べられた。地方創生とは、人口減少や高齢化、東京一極集中などの課題に直面する日本の地方に活力を取り戻すための取り組みのこと。
「地方の経済が盛り上がらないと日本全体が盛り上がらない」という認識のもと、地方創生2.0では特に「若者・女性に選ばれる地方」の創出を目指している。「石破政権は国家戦略に地方創生のためのWeb3をうたっているので安心してこの業界を推し進めてください」との発言からは、政府のWeb3技術活用へのコミットメントが感じられた。
成功事例と実際のアプローチ
具体的な成功事例として、中越地震で衰退した山古志村の「錦鯉NFT」プロジェクトが紹介された。この取り組みは、地方創生2.0が掲げる「地域資源を活用した高付加価値型産業の創出」という方針に合致している。
一方で行政側の理解不足も課題として議論された。「行政担当者が毛嫌いする状況をどう切り崩すか」という問題に対し、以下の対応策が提案された。
- 成功事例を提示する(北海道や鳥取など)
- 市長に直接アプローチする(政治家経由も効果的)
本イベントを通じて、Web3技術が地方創生2.0と高い親和性を持つことが明らかになった。特に地方創生2.0の「デジタル・新技術の徹底活用」では、ブロックチェーン技術やNFTの活用が明記されている。
「付加価値創出型の新しい地方経済の創生」においても、Web3技術を活用した地域資源の価値化や域外需要の取り込みが重視されており、山古志村の錦鯉NFTはまさにこの方針に合致した好例と言えるだろう。
ネットワーキングセッション

トークセッション終了後には、参加者同士の交流を深めるネットワーキングセッションが開催された。豪華な食事が用意される中、参加者たちは熱気あふれる雰囲気の中でコミュニケーションを図り、業界の最新動向や今後の展望について活発な意見交換が行われた。

業界の第一線で活躍する専門家や企業代表者、政府関係者が一堂に会したこの貴重な機会は、参加者にとって新たなビジネス関係の構築やプロジェクト連携の可能性を探る場としても大いに活用された。国内外からの参加者が入り混じり、言語や文化の壁を超えた対話が続いた様子は、Web3業界の国際的な広がりと今後の発展性を象徴するものだった。

本イベントの共催・スポンサー企業について
BitGo
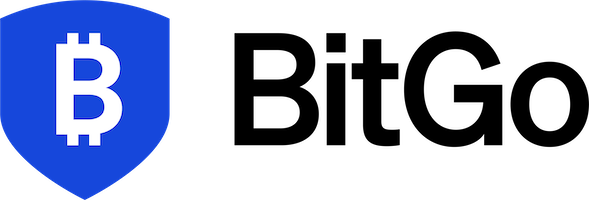
BitGoは、デジタル資産ソリューションのリーディングカンパニーであり、規制に準拠したコールドストレージを基盤としたカストディ、ウォレット、ステーキング、トレーディング、ファイナンス、決済サービス等を提供しています。2013年の創業以来、当社は顧客がデジタル資産を安全に活用できるよう支援することに注力しています。BitGoはグローバルに展開し、複数のトラスト会社を運営しており、業界を代表する取引所やプラットフォームを含む世界100カ国以上、3,900以上の機関投資家、および世界中の何百万もの投資家にサービスを提供しています。デジタル経済のオペレーショナルバックボーンとして、BitGoはビットコイン取引の約20%を処理しており、世界最大の独立系デジタル資産カストディアンおよびステーキングプロバイダーです。
代表者:Mike Belshe
所在地:South Dakota, USA
設立:2013年
公式サイト:https://www.bitgo.com/
X(旧Twitter):https://x.com/BitGo
Youtube:https://www.youtube.com/@BitGo.
LinkedIn:https://www.linkedin.com/company/bitgo-inc/
GSR

GSRは暗号資産市場において10年以上の豊富な実績を有するグローバルマーケットメーカーです。ヨーロッパやアメリカを含めグローバルにプレゼンスを持ち、アジアではシンガポールを拠点として展開しています。流動性プロバイダーおよびマルチステージ投資家として活躍しており、一連のサービスには、OTCトレーディング、デリバティブ、マーケットメイキングが含まれます。GSRは、トークン発行者、機関投資家、マイナー、主要取引プラットフォームと連携し、デジタル資産エコシステムの主要分野に積極的に関与しており、クリプトネイティブ起業家やデジタル資産へ進出する大手金融機関との強固な協力体制があります。なお、GSR Markets Pte. Ltd.は、シンガポール金融管理局(MAS)から主要決済機関(MPI)と英国金融規制当局(UK FCA)から暗号資産取引業のライセンスを取得しています。
公式サイト :https://www.gsr.io/
X(旧Twitter):https://x.com/gsr_io?lang=en
Figment

Figmentは、ステーキングインフラを提供する独立系プロバイダーとして業界をリードしています。資産運用会社、取引所、ウォレットプロバイダー、財団、カストディアン、そして大口トークンホルダーなど、700社以上の機関投資家のデジタル資産約150億ドルのステーキングを担っています。イーサリアムにおいては非カストディ型ステーキングプロバイダーのうち最大シェアを誇ります。
Figmentの機関投資家向けワンストップステーキングサービスには、シンプルなワンクリックステーキング、ポートフォリオ報酬トラッキング、API連携、監査済みインフラ、スラッシング保護などが含まれます。これらすべては、デジタル資産エコシステムの普及、成長、そして長期的な成功を支えるというFigmentのミッションの実現に貢献しています。
代表者:Lorien Gabel
所在地:545 King Street West, Toronto, Canada
公式サイト:https://figment.io/company/about/
X (旧 Twitter):https://x.com/Figment_io
Linkedin:https://www.linkedin.com/company/figment-io/
Youtube:https://www.youtube.com/@Figment_io
Halborn
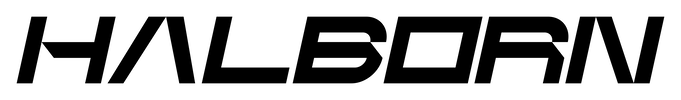
大手金融機関やWeb3エコシステムのリーダー企業から信頼を受けるHalbornは、エンタープライズグレードのデジタル資産向けブロックチェーンソリューションを提供する業界最先端の企業です。スマートコントラクト監査、ペネトレーションテスト、各種アドバイザリーサービスをはじめ世界トップクラスのセキュリティソリューションを提供します。
公式サイト: https://halborn.com/
X(旧Twitter):https://twitter.com/HalbornSecurity
LinkedIn:https://www.linkedin.com/company/halborn
Youtube:https://www.youtube.com/c/Halborn
Messari JAPAN

Messariはユーザーが自信を持ってデジタル資産/web3市場をナビゲートできるよう、マーケット・インテリジェンス製品プロバイダーとして2018年に設立され、以来デジタル資産市場のリーディングカンパニーとして認知されています。グローバルなリサーチ・データベース、包括的なデータの可視化、プロトコル調査などの資産発見ツール群を組み合わせることで、業界に透明性とよりスマートな定性・定量分析をもたらします。世界各国のトップティアVCや大手プロジェクトに留まらず、機関投資家から個人、業界外のプレイヤーまで、デジタル資産へのスマートな参加と意思決定を促進します。同社のオープンソースデータライブラリは、研究者、投資家、規制当局が業界への理解を深め、暗号資産市場の拡大やより良い社会の実現に向けた政策提示に活用されています。
公式ウェブサイト:https://messari.io
X(旧Twitter):https://twitter.com/@MessariCrypto
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/messari/
総合お問合せ:info@messari.io
メディアお問合せ:press@messari.io
plume

Plume Networkは、RWAfi(現実資産トークンファイナンス)のために特別に設計された初のフルスタックL1 RWAチェーンとエコシステムであり、リアルワールドアセットの速やかな導入と需要に基づく統合を促進します。
公式ウェブサイト : https://plumenetwork.xyz/
株式会社DeFimans

web3業界で実業経験を積んだメンバーによって設立されたDeFimansは、トークンエコノミクスの構築やブロックチェーン技術の活用等、web3領域に特化したハンズオン型のプロフェッショナルファームです。web3ビジネスでの“信用”を創造し、クライアントと共に日本のweb3業界の発展に向けて歩み続けます。
代表者:代表取締役 小野 暢思・佐藤 太思
所在地:東京都港区虎ノ門5丁目3−1 第一榎ビル 4F
設立:2022年7月
事業内容:
トークノミクス、DeFi、GameFi・ブロックチェーンゲーム、海外展開、事業戦略、新規事業開発、ブロックチェーン社会実装、NFT、dApps、DAO等に係るコンサルティング支援
資金調達・資本政策、マーケティング、翻訳等のハンズオン支援、Messari JAPAN運営
公式サイト:https://defimans.com/
X(旧Twitter):https://twitter.com/DeFimans
note:https://note.com/defimans
Medium:https://medium.com/@DeFimans
総括
「DeFimans Fintech & web3 Night」では、国際的Web3企業と政府関係者が集い、DeFiとCeFiの融合、米国と日本のWeb3政策、そして地方創生2.0との連携について議論が交わされた。
石破政権のWeb3活用方針が確認され、山古志村の「錦鯉NFT」等の成功事例が共有された。一方、Web3企業と金融機関の協業や政策協調、地方創生活用、行政啓発など課題が明確になった。



 はじめての仮想通貨
はじめての仮想通貨 TOP
TOP 新着一覧
新着一覧 チャート
チャート 取引所
取引所 WebX
WebX



























































