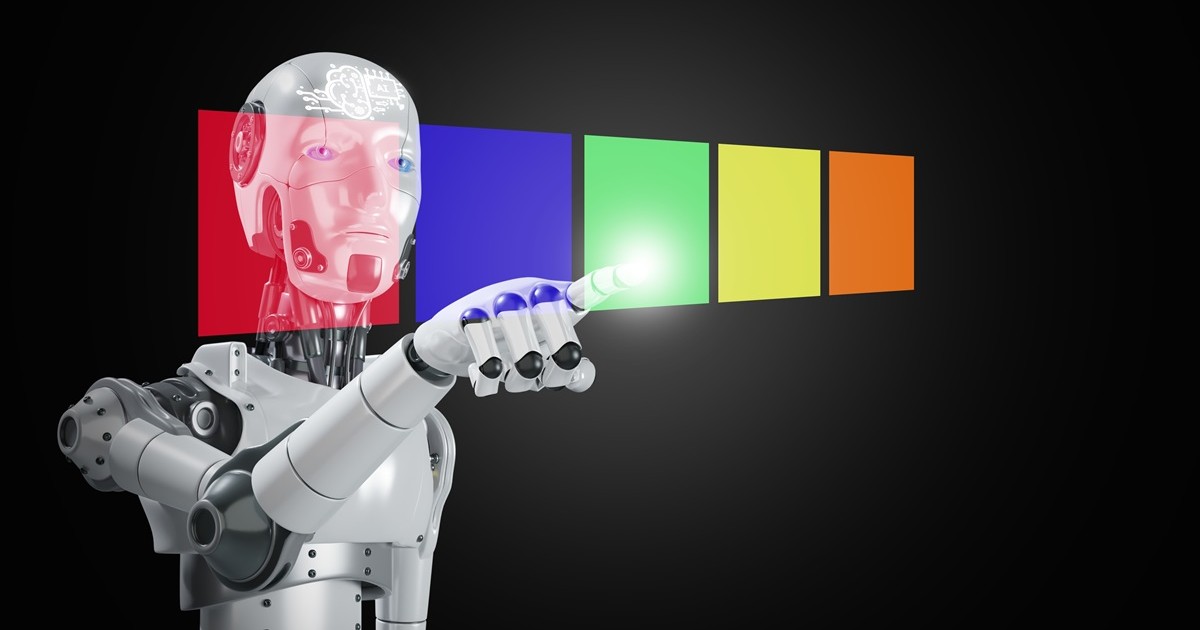
ユースケースから探る実現可能性と課題
米大手ベンチャーキャピタル企業アンドリーセン・ホロウィッツ(a16z)は11日に公開した最新レポートで、人工知能(AI)と暗号資産(仮想通貨)の交差点について、現在開発されているテクノロジーを基盤とした11の具体的なユースケースを提示した。
a16zは、急速に発展するAIを支える経済構造によって、巨大企業によるインターネットの中央集権化が進む中、ブロックチェーンの分散型ネットワークは、その経済構造を再構築し、よりオープンで堅牢なインターネットの実現に貢献すると指摘した。
仮想通貨がより優れたAIシステムの構築に役立ち、逆もまた真と考えられているが、その定義は曖昧であるため、具体的なユースケースを示すことを通して、実現可能性や今後の課題について議論のきっかけを作る目的でこのレポートが執筆された。
レポートでは、大きく分けてアイデンティティ、AIのための分散型インフラ、新たな経済・インセンティブモデルという三つの領域に加え、AIの将来の考察を加えた以下の11のユースケースを紹介した。
- アイデンティティ
- 永続的なデータとコンテキスト
- エージェントのためのユニバーサルID
- 人間性の証明
- AIのための分散型インフラ
- AIのためのDePIN
- AIエージェント間のインタラアクションの基準
- バイブコーディングアプリの同期
- 経済・インセンティブモデル
- マイクロペイメント
- 知的財産と出所の登録にブロックチェーンを利用
- バイブコーディングアプリの同期
- コンテンツ制作者の報酬サポート
- パーソナライズされプライバシーも保護された広告
- AIコンパニオン
アイデンティティ領域
アイデンティティに関するユースケースでは、まず、異なるAIプラットフォーム間でコンテキスト(文脈)を共有するためのブロックチェーン利用を取り上げた。例えば、ゲームやメディア(難易度やキー設定の保存)、知識ベースのアプリケーション(ユーザーの知識や学習方法の理解)、コーディングなどプロフェッショナルな用途におけるコンテキストを、ブロックチェーンに永続的なデジタル資産として保存。AI間でユーザー情報を共有することで、ユーザー体験を最適化することが可能になる。
現在は、プラットフォーム(アマゾンやフェイスブックなど)ごとに独自のアイデンティティ(人やモノの記録)管理を行なっているが、顧客対応や物流、支払いなどでAIエージェントの使用が普及するにつれ、単一のアプリやプラットフォームに縛られない多様な環境で動作するエージェントが必要になる。その際に、エージェントを支えるのが、共有されたアイデンティティの基盤となる、プラットフォームに限定されないポータブルな「パスポート」だ。
また、ボットやディープフェイクなどの機能を支えるAIの普及により、インターネット上では「本当に人間かどうか」の判別が困難になりつつある。そこで、ブロックチェーンを活用し、ユーザー自身が管理する分散型の「人間証明」メカニズムに注目が集まっている。プラットフォームに依存しないポータビリティと、パーミッションレスのアクセスという機能を備える。
AIのための分散型インフラ
AIのための分散型インフラの筆頭は、分散型物理インフラネットワーク(DePIN)で、AIの進化のネックとなっていた電力や高性能チップへのアクセス制限という課題を解決する。
また、AIが進化する中でAI同士が自律的にやり取りしながら、複雑なタスクをこなすようになる時代が到来すると考えられるが、現在はAIエージェントのほとんどがサイロ化されたエコシステム内で動作しており、共通のインフラは存在しない。そこでブロックチェーン技術によってAI間の共通プロトコルを構築し、誰でもアクセスできるオープンな基準を整備することで、相互運用可能なネットワークの実現に期待が集まっている。c
生成AIの進化により、ソフトウェア開発が劇的に高速化し、初心者でも自然言語でコーディングやカスタムアプリの作成が可能になった。しかし、このような「バイブコーディング」(直感的なAI支援コーディング)ではプログラム機能やセキュリティに問題が起きる可能性があり、カスタムアプリの互換性も低下する。従来の標準化では、リアルタイムで進化するソフトウェアに対応できないが、ブロックチェーンを活用し、同期レイヤーを共有所有することが解決の鍵となる。
新たな経済・インセンティブモデル
AIツール(ChatGPT、Claude、Copilotなど)は便利だが、教育プラットフォームのトラフィック減少や新聞社によるOpenAIへの著作権訴訟に見られるように、インターネットの経済を不安定にしている。インセンティブを再調整しなければ、インターネットはますます閉鎖的になり、有料コンテンツが増え、コンテンツクリエイターの減少が懸念される。
技術的な解決策として、Webの構造に収益分配を組み込む方法が有望であり、AIの行動が売り上げにつながった場合に、コンテンツの提供元に収益を分配する仕組みが考えられている。ブロックチェーンの利用により、情報の出所を追跡し、コンテンツ提供者への少額支払いや取引後の遡及的支払いを、スマートコントラクトによって公平に実行することが可能になる。
生成AIの登場により、知的財産(IP)の所有権や出所をどのように証明・管理するかが大きな問題となっている。必要とされているのは、所有権の明確な証明を提供し、IP作成者が容易に操作できると同時に、AIやWebサービスが直接操作できる、オープンで公開された登録簿だ。ブロックチェーンを活用したプログラム可能なIPインフラによって、クリエイターやブランドがデジタル空間でIPの所有権を明確にできるだけでなく、生成AIなどでのIP利用を前提とした新たなビジネスモデルを作ることも可能になる。
インターネットトラフィックの約半分を占めるWebクローラー(Webサイトを巡回し、情報収集するボット)が、サイト運営者に帯域やCPUコストを負担させ大きな問題となっているが、ブロックチェーンを活用した解決策が提案されている。コンテンツ配信ネットワーク(CDN)に対し、AIボットが仮想通貨で、情報収集権利の対価として金銭的支払いを行うというものだ。ただし、CDNの参加やこれまでのインターネットの慣習の変更など、大規模な協調が必要となる。
ブロックチェーンとAIを組み合わせることで、ユーザーの好みに基づいた適切な広告を、プライバシーを守りながら配信できる新しい仕組みが提案されている。広告の閲覧やクリックに対する少額支払い(高速で手数料はほぼゼロのシステムが必須)は、プライバシーが保護されたデータ検証やユーザー参加型のインセンティブモデルなどが、実現のための技術的要件となる。
コンパニオンとしてのAI
現代人の多くにとって、実際の対面での交流よりも、デバイスを介してAIモデルやAIが選別したコンテンツと過ごす時間が増えている。近い将来、教育、医療、法律相談、そして友情といった分野でAIベースのコンパニオンが、人間にとって一般的になる可能性がある。この未来のAIコンパニオンは、忍耐強く、特定の個人や用途にカスタマイズされるため、「価値ある関係性」に発展することも考えられる。
そのため、このような関係性における所有権や制御権が、ユーザーに属するのか、企業や仲介者に握られるのかが、重要な問題となる。ブロックチェーンは、検閲耐性のあるホスティングプラットフォームとして、ユーザーが制御可能なAIを実現する最適な手段となり得る。
ブロックチェーンはより高性能になっており、すでに、Phantomのようなウォレットや、パスキー、アカウント抽象化により、ユーザーは複雑なシードフレーズ管理なしに自己管理ウォレットの保有が可能になっている。また、テキストベースの人間らしいコンパニオンやビジュアルアバターは大幅に進化している。
a16zは、近い将来、我々の話題は、「いつリアルなデジタルコンパニオンが登場するか」から、誰がそれをコントロールするのか」に移っていくだろうと締めくくった。



 はじめての仮想通貨
はじめての仮想通貨 TOP
TOP 新着一覧
新着一覧 チャート
チャート 取引所
取引所 WebX
WebX


























































