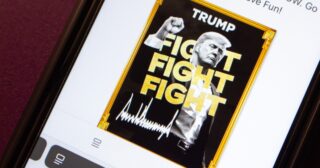11月7日、金融庁の金融審議会「暗号資産制度に関するワーキング・グループ」第5回会合が開催され、暗号資産規制の金融商品取引法への移行を軸とした制度改革が大詰めを迎えている。
銀行グループ子会社による暗号資産交換業への参入、インサイダー取引規制の導入、分散型取引所(DEX)への対応など、包括的な規制の見直しが議論されている。
そんな中、金融庁担当者に独自取材を実施。制度改革の狙いや期待する効果、今後の展望について伺った。
銀行グループ子会社の暗号資産交換業参入
銀行グループ子会社の暗号資産交換業参入について、想定されるメリット・デメリットは
金融庁:現在、暗号資産制度に関するワーキング・グループにおいて、暗号資産の売買等を金融商品取引法上の金融商品取引業に位置付けることを検討していることを踏まえ、銀行グループにおける暗号資産交換業等の考え方の整理を行っています。
銀行本体においては、暗号資産に関連する取引を営むことの各種リスク──マネー・ローンダリング等に利用されるリスク、暗号資産の管理等にかかるシステムリスク、暗号資産の保有に伴う価格変動リスクのほか、これらのリスクが顕在化した場合のレピュテーショナル・リスク等──や、銀行本体が扱っている商品であることを以て、暗号資産のリスクや自らのリスク許容度を精査せずに取引してしまう顧客が一定数生じるおそれがあること等から、銀行本体による暗号資産の売買等を認めることについては、依然として慎重な検討が必要であると考えています。
一方、銀行グループの金融商品取引業者であれば、銀行本体との関係で一定のリスク遮断が図れることや一般の金融商品取引業者とのイコールフッティングを図ることが適当であると考えられること等を踏まえ、暗号資産の売買等を認めることを検討しています。
銀行グループの金融商品取引業者と一般の金融商品取引業者のイコールフッティングを図ることで、同じ競争環境での取引が可能となるメリットがあると考えています。一方、暗号資産交換業を行うグループ会社において、例えば、暗号資産が不正流出する事案が発生した際に、レピュテーショナル・リスクが銀行グループ全体に波及するといったデメリットがあると考えています。このため、そうしたリスクを管理できる態勢が整備されているか等を確認する必要があると考えています。
金融システムの安定性への影響は
金融庁:現行制度において、銀行グループによる暗号資産の取得については、その健全性の確保等の観点から、監督指針において必要最小限度の範囲とするよう求めています。
今般の見直しにおいても、銀行グループが暗号資産取引を行うに際しては、銀行本体の経営の健全性や金融システムの安定性に直接影響することのないよう、銀行本体が暗号資産を保有する場合には十分なリスク管理・態勢整備等が行われていることを求めること、そして暗号資産の売買等については、銀行本体ではなく銀行グループの金融商品取引業者が行うことを検討しています。
今般の暗号資産制度に関するワーキング・グループでの議論も踏まえながら、さらに検討を深めてまいります。
インサイダー取引規制
インサイダー取引規制の導入で期待する効果は
金融庁:暗号資産の投資対象化が進展する中で、暗号資産交換業者の提供する取引の場の公正性・健全性に対する投資者の信頼を確保する観点から、諸外国の状況なども参考に、暗号資産に係るインサイダー取引規制の導入を検討しています。
投資商品としての暗号資産を巡る制度を整備する中で、インサイダー取引規制を含む不公正取引規制を設けるとともに、こうした規制について実効性を確保し健全な取引環境を実現していくことが、我が国における健全なイノベーションにもつながり得ると考えています。
分散型取引所(DEX)への対応
分散型取引所への規制について、主な狙いは
金融庁:DEXと呼ばれる分散型取引所は、利用者に暗号資産同士の交換を可能とするものであり、その提供するサービスの暗号資産交換業の該当性が論点となりえます。
分散型取引所は、プロトコルの開発後はスマートコントラクトにより自動で暗号資産売買の仲介がなされることにより、人為的な要素が少ないなどの特徴がある一方で、海外においては、プロトコルの不備などにより流動性供給者の暗号資産が流出するなどの事態が発生している他、本人確認の未実施によるマネー・ローンダリングリスクも指摘されています。
こうしたことから、金融庁としては、今後は各国の規制やその運用動向も注視しながら、開発後はプロトコルの変更が出来ない分散型取引所を開発・設置する者等に対して、技術的な性質に合わせた規制の在り方について、継続的に検討を行っていくことを論点として提示いたしました。
利用者が分散型取引所に接続することを容易にするUI(ユーザーインターフェース)の提供事業者への対応については、分散型取引所に接続することで利用者が上述のような事態により損害を被るリスクに留意する必要がある一方、分散型取引所やこうしたUI提供事業者に係るAML/CFT対策の在り方についての国際的な議論を引き続き注視していく必要があると考えており、例えば、UI事業者において犯収法上の本人確認義務を含むAML/CFT対策を講じることで、分散型取引所に関するマネー・ローンダリングリスクを低減させることができるとの議論もありうるところです。
このため、金融庁として、UI事業者に対して接続先のリスク(プログラムの不備等により利用者が不測の損害を被るリスク等)についての説明義務や本人確認義務も含めたAML/CFT対策等、過不足のない規制を課すことを念頭に、海外動向を注視しつつ、サービスの実態把握を進めていく必要があると考えています。
他方で、足元の対応として、まずは、行政や暗号資産交換業者において、日本で登録を受けていない業者で暗号資産の取引を行う場合のリスクについて、利用者に対し、十分に周知を図っていきたいと考えております。
金融審議会過去の記事
第一回:金融庁が仮想通貨WG第1回会合を開催、金商法活用で本格検討へ
第二回:暗号資産制度に関する第二回「金融審議会」、有識者の委員らが議論交わす
第三回:金融審議会が「第3回暗号資産WG会合」開催、上場審査プロセスにも言及



 はじめての仮想通貨
はじめての仮想通貨 TOP
TOP 新着一覧
新着一覧 チャート
チャート 取引所
取引所 WebX
WebX