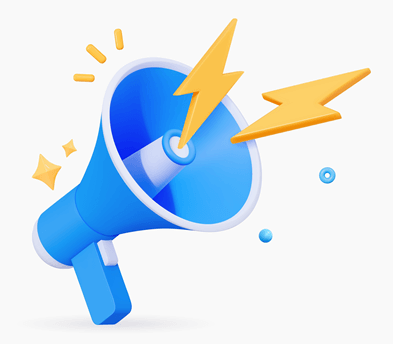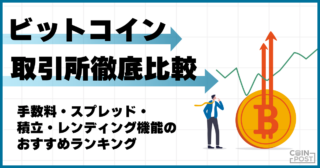オントロジーとは
オントロジーは、「信用の再定義」をミッションとして掲げ、分散型ID(アイデンティティ)ソリューションとデータ共有プロトコルに特化した、オープンソースなブロックチェーンを開発している企業です。
オントロジーは、スマートコントラクトシステムを含む、分散型パブリックブロックチェーンのプラットフォームを展開しており、独自のブロックチェーン技術をもとに、企業が抱える問題へのソリューションを提供します。
オントロジーのブロックチェーンではクロスチェーン取引も可能です。つまり、異なるブロックチェーン同士でもデータや価値のやりとりが可能で、企業ごとに異なるブロックチェーン技術を採用していたとしても、オントロジーを利用すれば企業間のコラボレーションが円滑に行えるようになります。
時間とコストのかかることが多いブロックチェーンの性質を克服するために、オントロジーは幅広い企業や組織にとって、より使いやすく効率的なオンボーディングを推進するための分散型データ交換フレームワークを提供します。
このフレームワークにより、企業の顧客は、安全性、透明性、コスト効率に優れた方法でデータを転送・交換できるようになります。
開発について
オントロジーの基盤技術は、中国版イーサリアムと呼ばれる「NEO」を開発するオンチェーン(Onchain)社が開発しています。
そのことからも、オントロジーはNEOと関係の深い仮想通貨であり、Binanceへの上場の際には、NEOの保有者へONTの配布が行われています。
オントロジーはNEOのネットワークを利用したプロジェクトでありますが、別の企業体が運営を行っていることに加え、開発目的も異なる為、NEOとは目的を異にする通貨と考えて良いでしょう。
オントロジー・ブロックチェーンの特徴
デュアルコイン・システム
メインネットのローンチ以降、オントロジーはネットワークのセキュリティと円滑な運営のために2種類のトークンを採用しています。
ONTはコンセンサスおよび他のガバナンス機能でのステーキングに使用できるトークンとして、そしてONGはオンチェーンサービスに使用されるユーティリティトークンとして利用されます。
オントロジーコイン(ONT)
ONTの総コイン供給量は10億ONTで、そのうち約80%が現在流通しています。
ONTは、オントロジー・ブロックチェーンのエコシステムの中で、トークン保有者にガバナンス投票権およびトークンをステークする権利を付与します。これらは、取引を検証することでネットワークのセキュリティを向上させる役割があります。
ユーザーがONTコインをノードにステークすると、基本的に1回の投票サイクルの間、スマートコントラクトにONTをロックすることになります。これにより、ブロックチェーンのブロック処理を行うコンセンサスに参加するノードを決める投票権が確保されます。
ONTコインをステークしたユーザーは、ステーク報酬が得られるため、オントロジー・ネットワーク運営の舵取りに一役買うだけでなく、プロジェクト関与からの利益を得ることもできます。ただし、ONTをステークした場合、ステーク報酬はオントロジー・ガス(ONG)で受け取ることとなります。
オントロジー・ガス(ONG)
ONGはオントロジー・ブロックが確認されるたびに生成され、基本的にオントロジーのメインネットを動かすガスとなります。それにより、ユーザーはブロックチェーンの運用維持に協力することで取引手数料を得ることができます。
ONGは、スマートコントラクトの実行など、オントロジー・ブロックチェーンの操作を行う際にも使用されます。
クロスプラットフォーム
オントロジーのクロスプラットフォームによる相互運用性は、2020年8月にNEOおよびSwitcheoが提携し、異種間相互運用性プロトコルアライアンス「PolyNetwork」が立ち上がったことで大幅に拡大しました。PolyNetworkの主な目的は、様々なデジタル通貨と他のトークン化された資産との交換といったクロスチェーン取引を、関連プロジェクトが効果的に行う能力を最大化することです。
NEOとの統合
オントロジーは2019年7月にNEOとのパートナーシップを発表しており、正式に統合されました。
NEOのプロジェクトにおける信頼性と、オントロジーの信頼性は比例するものであり、オントロジーのブロックチェーンによる技術・情報提供・管理は、相対的にNEOの市場評価に繋がります。
オントロジーは、独立性の高いデータベース同士の情報共有が可能であることに加え、ブロックチェーン技術を持たないあらゆる企業などに対して、ブロックチェーンへの参画を可能にします。
さらに開発面では、NEOは多様なプログラミング言語での開発が可能であるため、開発環境に行き詰ることはないというメリットがあります。
今後の将来性
Onchain社とは
オントロジーの開発者である「Onchain」社は、2014年に設立されてから、中国国内のIT・金融分野において高い評価を得ています。
Onchain社の設立者の一人であるDa HongFei氏は、「デジタル化された情報をブロックチェーンによって統合・管理できる」としたうえで、総合的にスマートな経済形成のために、ブロックチェーンの利用を前提とした社会を作ることを目標としています。
Onchain社は、ビジネスにおけるブロックチェーンの活用を推進しており、最終的には政府・企業との協力を目指しています。
そして、ブロックチェーンの国際開発コミュニティHyperledgerにも参加。現在では、IBMなどの世界の名だたるIT企業と共同し、ブロックチェーン技術の開発を進めています。
また、Onchain社の資本に目を向けてみると、世界的に有名な企業であるアリババと提携していることに加え、中国の中でもでもトップクラスの大企業と言えるFosun Groupからの融資も受け取っています。
つまり、資本面でも技術面でも、Onchain社は”優良な開発状況がすでに整っている”と言っても過言ではありません。
主な提携先
オントロジーは設立以来、そのブロックチェーン技術を基盤とした「信用の再構築」を目指してきましたが、これまでブロックチェーン業界内外の様々な企業と、積極的にパートナーシップを締結しています。その一部は以下の通りです。
マイクロワーカーズ(MicroWorkers)
マイクロワーカーズは、データ収集や分析、カテゴリー分類など、一般的な仕事やタスクより細かく分けられた小規模の「マイクロジョブ」に特化した、クラウドソーシングプラットフォームです。2009年に設立され、現在世界190カ国以上の企業およびフリーランサーが利用しています。
マイクロワーカーズとの提携が20年2月に発表された後、雇用主とフリーランサーを繋ぐクラウドソーシングプラットフォームにおけるウォレットとして、オントロジーのONTOが選ばれました。その結果、マイクロワーカーズを利用するフリーランサーは、仮想通貨での報酬・給料の受け取りが可能となっています。
関連:フリーランサーも仮想通貨で報酬受け取りが可能に、オントロジーがウォレット統合を発表
NEARプロトコル
20年8月に正式発表されたNEARとの提携では、DeID(分散型ID)の実用性が強化されています。NEARプロトコルとは、米サンフランシスコを拠点とするブロックチェーン基盤のdApps(分散型アプリ)開発プラットフォームです。
ダイムラー
20年9月には、ドイツ自動車大手のダイムラー(Daimler Mobility AG)と提携。この提携の目的は、ブロックチェーンを介したオントロジーのデジタルIDとデータライフサイクル管理技術を活用し、よりパーソナライズされたドライブ体験の実現です。
関連:分散型ネットワークのオントロジー、自動車大手ダイムラーと提携 デジタルドライブサービス提供へ
Polkadot
20年10月に発表された提携により、Polkadotブロックチェーン上に、オントロジーのDeID(分散型ID)ソリューションおよびOScoreが統合されています。OScoreとはオントロジーが開発した信用スコアシステムで、ユーザーの仮想通貨取引および資産管理の履歴に基づいた信用スコアを用いて、資産の貸し借りができるものです。
関連:オントロジーがPolkadotと協業、分散型IDを統合
バイナンス
オントロジーはバイナンスとの提携により、開発している分散型IDソリューションONT IDのフレームワークが、バイナンスのセキュリティトークンオファリング(STO)プロジェクトに採用されことを20年9月に発表しています。
関連:バイナンス、オントロジーと提携 「分散型ID」活用でSTO市場に新たな一手
ZAICO
21年6月には、日本の在庫管理ソフト企業、ZAICOと提携を発表。オントロジーのブロックチェーンが国内企業に取り入れられる事例としては、これが初です。
関連:Ontology(オントロジー)、国内の在庫管理ソフト開発企業と提携
主力プロダクトの2021年ロードマップ
オントロジーは、5つの主力プロダクトである、分散型IDプロトコル「ONT ID」、分散型レンディングサービス「Wing」、分散型信用評価システム「OScore」、仮想通貨・資産管理ウォレットアプリ「ONTO」、および分散型データ・マーケットプレイス「SAGA」の開発状況を公表しています。
20年はDeFi(分散型金融)への参入に注力しており、21年は自社プロダクトを他のチェーンと統合し、さらに多くのユーザーを取り込むことを目標としているとのこと。
分散型IDプロトコル「ONT ID」
ONT IDとは、オントロジーの分散型ID(DeID)ソリューションです。分散型IDとは、中央集権機関に頼らずに、ブロックチェーン技術を活用して分散的な方法で、アイデンティティ証明に必要な個人情報を管理する概念を指します。
ONT IDに関しては、他のパブリックチェーンとの統合、ならびにセキュリティおよびプライバシー管理機能の追加実装が計画されています。
2021年には、ONT IDプロトコルがさまざまなパブリックチェーンにエクスポートされ、チェーン間での分散型IDおよびデータプロトコルのより広い普及が見込まれています。
関連:自己主権型アイデンティティガイド|オントロジー(Ontology)寄稿
分散型レンディングサービス「Wing」
オントロジーは20年9月、「Wing」と呼ばれるレンディングに特化したDeFiプラットフォームをローンチ。
現在Wingでは、オントロジーのネイティブトークンONTなどをステークすることによりイールドファーミングを実施できる「Flash Pool」、および信用基盤のレンディングサービス「Inclusive Pool」の二つのプロダクトが利用可能となっています。
21年は新たなプロダクトをWing上で構築し、貸借および担保可能な資産の種類を増やしていき、その過程でNFT(Non Fungible Token/非代替性トークン)、現物資産、アート作品、デリバティブ商品、合成資産および証券などの取扱いも検討しているということです。
Wingでは、オントロジーの分散型信用評価システムOScore、分散型データフレームワークDDFX、および分散型IDプロトコルONT IDが活用されています。このような仕組みを利用することで、ユーザーは自身の個人情報に対する完全な管理権を維持しつつ、ユーザー間の透明性を向上させることができます。
関連:信用に基づくDeFiプラットフォームWing、オントロジーブロックチェーン上で稼働開始
分散型信用評価システム「OScore」
OScoreとは、オントロジーが開発した信用評価システムで、ユーザーの仮想通貨取引および資産管理の履歴に基づいた信用スコアを用いて、資産の貸し借りができるものです。
上述のサービスWingでは、オントロジーのOScoreが利用されています。オントロジーは、OScoreを活用することにより、ユーザーのプライバシーを維持し、データを保護しながら、過剰担保削減やマイクロレンディング、信用委任(Credit Delegation)サービスなど、新たな分野の開発に取り組む予定だということです。
仮想通貨・資産管理ウォレットアプリ「ONTO」
ONTOは、オントロジーが開発を行うクロスチェーン(異なる複数のチェーン)対応の仮想通貨ウォレットです。ONTOは現在、オントロジー独自のオントロジーブロックチェーンを初めとする、ビットコイン、イーサリアムおよびバイナンススマートチェーンなど、14のブロックチェーンをサポートしています。
オントロジー開発のウォレットアプリONTOでは、サポートするdApp(分散型アプリケーション)およびDEX(分散型取引所)の数を増やし、異なるチェーンにも対応できるようにするとのことです。ONTOを利用しているDeFiユーザーは、他のウォレットを使用せずに、様々なチェーンのDeFiプロダクトにアクセスできるようになるようです。
分散型データ・マーケットプレイス「SAGA」
SAGAとは、オントロジーが20年5月に発表した分散型データプロトコルで、ユーザーは規格化された方法でデータの獲得、および収益化が可能です。SAGAは21年においては、主にリサーチに尽力し、実用的なユースケース開拓に焦点を当てるとのことです。
関連:オントロジーが分散型データ取引所「SAGA」をローンチ、成長著しい産業にアプローチ
国内取り扱い取引所
ディーカレット
株式会社ディーカレットは21年7月13日、オントロジー(ONT)の取り扱い開始を発表しており、これが国内仮想通貨取引所での初上場のケースとなりました。
ディーカレットで板取引可能な銘柄は、現在ビットコイン、イーサリアム、XRPの3種類です。
オントロジーの取り扱いがある取引所は日本国内では現在、ディーカレット一箇所のみとなります。
関連:ディーカレット、国内初となる仮想通貨オントロジー(ONT)の上場予定を発表
まとめ
「信用の再定義」をミッションとして掲げるオントロジーは、主に5つのプロダクトを通して、分散型ID(アイデンティティ)ソリューション、そしてデータ共有プロトコルを提供するブロックチェーン開発企業です。
オントロジーのサービスの中核となるパブリック・ブロックチェーンには大きな変化はないものの、企業やコミュニティが運営するコンセンサスや候補ノードを追加導入することで、分散型ネットワークのセキュリティを向上させることに重点が置かれています。
オントロジーのガバナンスモデルにおいては、ユーザーがパブリック・ブロックチェーンのガバナンスに参加し、ノードの運営や出資への敷居を低くしています。これにより、すでに確立されている高いパフォーマンスに加え、安全性と安定性を提供します。
さらに、2021年にはより柔軟なステーキングメカニズムや、さまざまな種類のスマートコントラクトのサポートも追加される予定です。オントロジーのコア技術チームは、既存のエコシステムを補完するために、DeFiとDeIDを掛け合わせた、さらに革新的な製品を生み出すことを目指しています。



 はじめての仮想通貨
はじめての仮想通貨 TOP
TOP 新着一覧
新着一覧 チャート
チャート 学習-運用
学習-運用