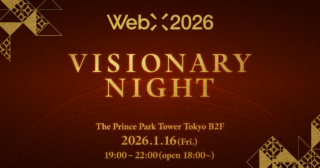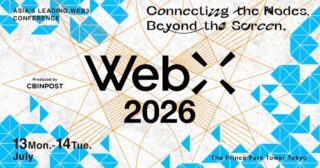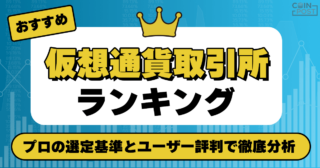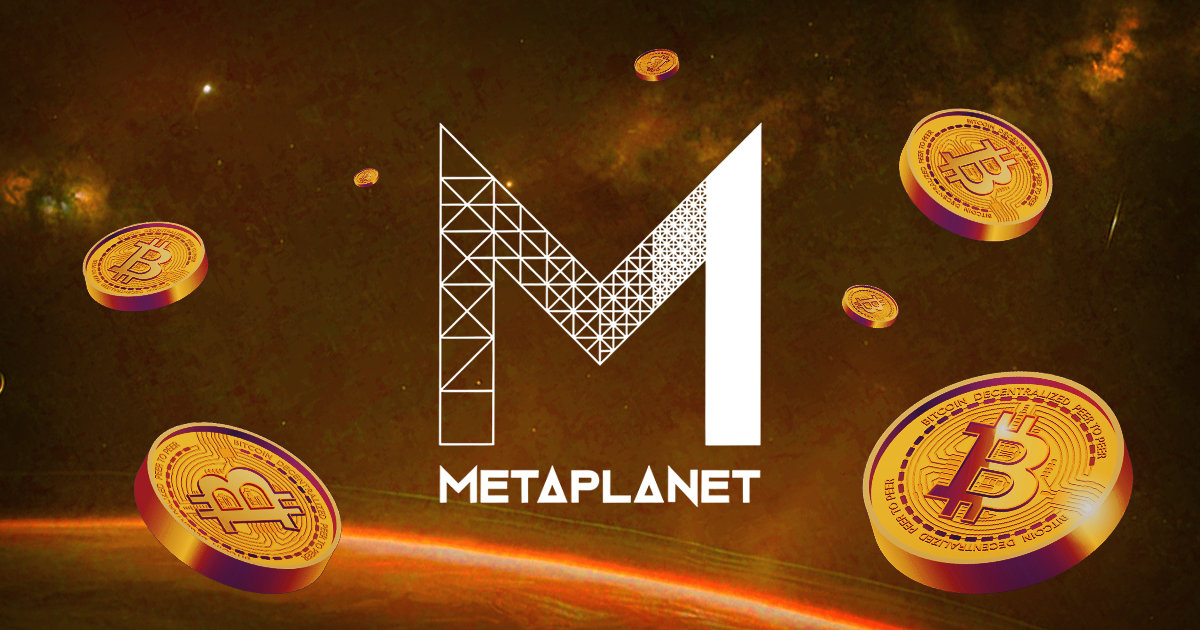
メタプラネット、株価は下値模索
東証スタンダード上場のメタプラネット(3350)は、10月17日に株価が400円台まで下落。年初来高値(約1,900円)から大幅安となり、BTC保有価値(NAV)に対して企業価値が割安となる「mNAV割れ(0.89)」の状態に陥っている。
mNAVとは
mNAV = (時価総額 + 総負債) ÷ ビットコインNAV(保有BTC時価総額)この値が1を下回るということは、市場が企業を「保有するビットコインの価値よりも低く評価している」ことを意味する。通常、この状態では新株発行による資金調達が困難になる。
ビットコイン価格の上昇を手掛かりにした年前半の物色人気が一巡し、ここ最近の株価は右肩下がりの展開に。依然として下値模索が続くなか、目先は売りを予想する向きが増えている。
サイモン・ゲロヴィッチCEOは17日、自身のSNSで「普通株を増やさず、優先株を活用してBTC保有量を増やす」方針を再確認。同社が採用する「永久型優先株」は償還期限を持たず、返済義務のない資本調達手段である。
サイモン氏は、“BTCリターンと資本コストの複利差が企業価値を押し上げる”という考えを数式化して説明した。BTCの年平均上昇率を30%、優先株の配当率を6%と仮定した場合、その差(24%)が毎年積み上がり、10年後にはBTC保有価値(NAV)が約13.8倍に拡大する一方で、6%の資本コストは約1.8倍にとどまる。
この差、約8倍の純増分がmNAV(1株あたりBTC保有価値)に反映される、という理屈だ。(※BTCの高成長が長期的に続くことを前提とした理論モデル)
一方で、投資家の関心は自社株買いなど短期的な株主保護策にも集まっている。株価が回復しない限り、CEOが掲げる「長期的な複利成長モデル」と市場の要求との間にはギャップが残る。
優先株・インカム事業の仕組み
「優先株」とは普通株とは別クラスの株式で、メタプラネットが採用する「永久型優先株」は償還期限を持たない。返済義務を負わずに長期的なBTC購入資金を確保でき、普通株を増やさず資本を厚くできるため、1株あたりBTC(mNAVの基礎)やEPSの希薄化を防げる。
また、配当率(=資本コスト)6%の原資を支えるのがBTCインカム事業。同社は現金担保付ビットコイン・オプションを組成・売却し、受け取るプレミアム収益を安定収益源としている。2025年第3四半期の売上高は24.4億円と前期の約2倍に拡大し、優先株配当を賄う実質的なキャッシュフローの柱となっている。
「PHASE II」で永久型優先株を採用
メタプラネットは10月1日、次の成長段階となる「PHASE II」を発表。2026年末までに10万BTC、2027年末までに21万BTCを保有する「555ミリオン計画」を据え置きつつ、株式の希薄化を抑えた資金調達手段として永久型優先株を導入する方針を明らかにした。発行上限はBTC NAVの25%(約1,250億円)に設定済みで、制度設計と登録は完了している(実際の発行額・条件は未確定)。
過去に調達した資金はすべてBTCの追加購入に充当。累計5,000億円超を調達し、保有BTCは30,823枚(約5,000億円相当)に到達。2025年度の目標(3万BTC)を前倒しで達成している。
メタプラネット主要指標(2025年10月17日時点)
- 株価:404円(前日比−6.05%)/年初来高値(約1,900円)から79%安
- 時価総額:約4,448億円(BTC保有価値=NAVを下回る水準)
- BTC価格:約1,632万円
- BTC保有数:30,823 BTC(約5,031億円)
- mNAV:0.89
- 総負債:約38億円
- 未実現損益:約133億円
依然としてmNAVは1を下回る「ディスカウント状態」が続く。サイモンCEOの掲げる“複利モデル”が実際に成果を上げられるかは、今後の資金調達の透明性とBTC相場の行方、そして短期的な信頼回復策をどれだけ素早く示せるかにかかっている。
関連:ビットコインを保有する上場企業ランキング|日本・米国の注目企業を解説



 はじめての仮想通貨
はじめての仮想通貨 TOP
TOP 新着一覧
新着一覧 チャート
チャート 学習
学習 WebX
WebX