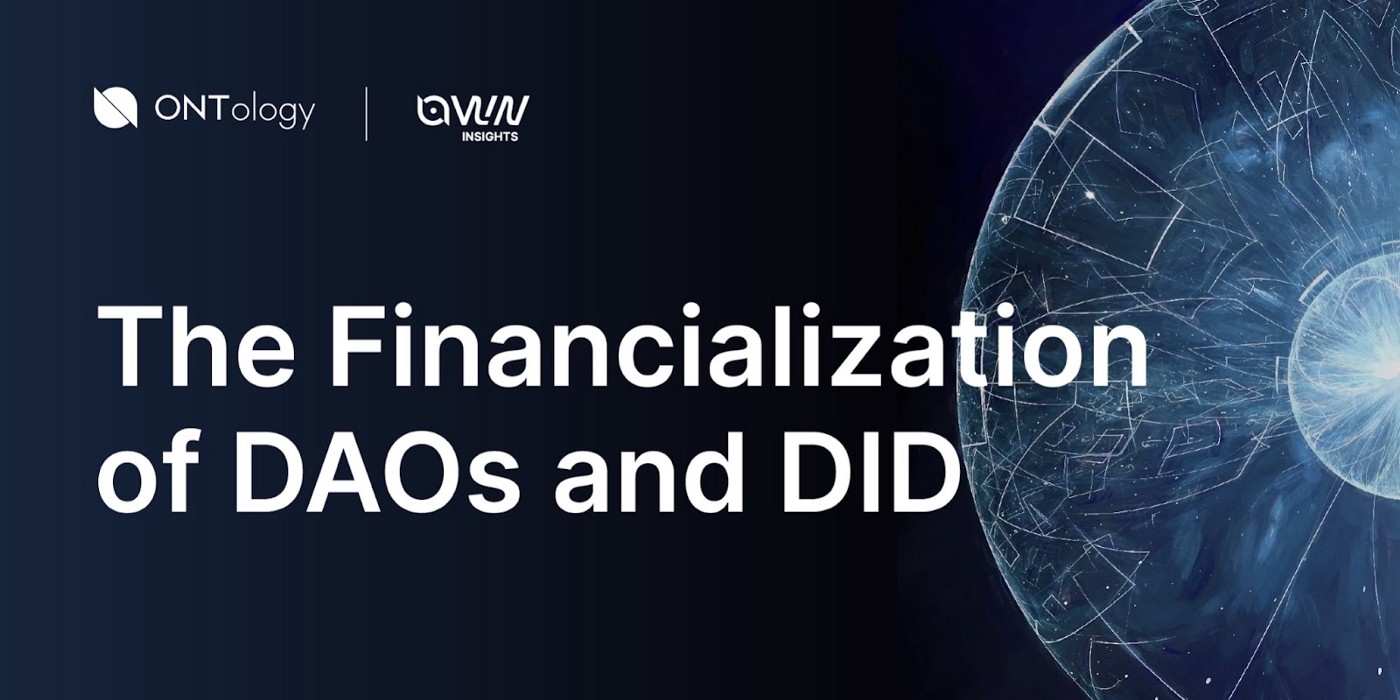
DAOと分散型IDが普及するには
オントロジーのOWN Insightsシリーズでは、業界のリーダーを招き彼らのWeb3産業についての知見を共有して頂いています。シリーズ全体を通して彼らの考えを学ぶことで、インターネットの新しい流れをより深く理解することができるでしょう。
今回は、オントロジーの米国エコシステム開発リーダーであるエリック・ピノス氏に、「Web3の実現」をテーマに寄稿いただきました。
DAO(自律分散型組織)は、2014年にイーサリアム創設者のヴィタリック・ブテリン氏によって提案され、長らく暗号資産(仮想通貨)市場特有の組織形態として理解されていました。しかし、2021年には米ワイオミング州ではDAOの法人化を正式に認める法案が承認されるなど、近年仮想通貨市場以外の関心も集めています。
関連:米ワイオミング州、自律分散型組織(DAO)の法人化法案が成立
分散型ID(DID)に関しては、2021年ごろから語られるようになり、2022年にはWeb技術の標準化団体であるWorld Wide Web Consortium(W3C)が分散型IDの標準規格を定めています。
関連:W3Cが取り組む分散型ID(DID)標準化とは=XSL Labs寄稿
しかし、DAOと分散型IDは、DeFi(分散型金融)やNFT(非代替性トークン)と比べて、まだまだ普及しているとは言い難い状況です。本記事では、DAOや分散型IDが広く普及するためにはどうすれば良いのかが解説されています。
DAOと分散型IDの「金融化」
Web3は、より分散化されたインターネットの次なる段階を表す、相互に接続された一連のテクノロジー、プロトコル、コンセプトやフレームワークを指します。近年、DeFiとNFTを通じて、Web3が実現する未来を垣間見ることができました。
この2つの技術は、全く新しい種類のオンラインP2Pによるコミュニケーションを実現しています。DeFiは、金融機関などの第三者による仲介を必要とせずに金融商品へのアクセスを可能とし、NFTはゲーム内資産、デジタルアート、知的財産などの暗号資産の所有権を証明することを可能にしました。
しかし、DeFiとNFTはWeb3を構成する多くの要素のうちの2つに過ぎません。これら以外にも重要な要素として、Web3インフラの創造における分散的な調整の役割を果たす「DAO(自律分散型組織)」、そしてWeb3サービスと相互作用しながら自身のデータを自己主権化するための「分散型ID(DID)」が含まれています。
DAOや分散型IDといったWeb3の要素が、DeFiやNFTのように普及するため何が必要なのかについては、DeFiやNFTがどのように普及したのかという歴史をもとに推測することが可能です。
分散型ID(DID)とは
分散型IDとは、中央集権的な身分証明証の発行機関や組織などに依存することなく、自分が誰であるか、また自分に関する情報や保有する資格などを証明・管理することのできる、新たなタイプのIDを指す。
DeFi
DeFiが最も人気のあるブロックチェーンのユースケースとなったのは2020年後半からですが、有名DeFiプロジェクトの多くは、この数年前から存在していました。
MakerDAOは2017年に、Uniswap・Compound・Aaveは2018年に、1inchは2019年にローンチしています。こうしたサービスは、ローンチ時から本来の目的で利用することができる状態にありましたが、サービス利用自体は「イールドファーミング」と呼ばれる機能が導入されてから本格化し始めました。
実際、2020年はイールドファーミングが仮想通貨業界を席巻しました。自身が保有する仮想通貨でトークンを獲得できるという展望は、多くの億万長者を生み出し、迅速にユーザーベースを拡大しようとする新興DeFiプロジェクトから多大な注目を集めました。その結果、短期間のうちにこの状況をうまく活用しようとするプロジェクトが続々と立ち上がりました。
分散型取引所や流動性アグリゲーター、そしてDeFiレンディングやデリバティブまで、ほとんどのDeFiプロジェクトがプラットフォームに流動性を提供するためのトークンインセンティブをユーザーに付与することで、ユーザーとTVL(Total Value Locked)を大幅に押し上げることに成功しました。
金銭的なインセンティブを付与することで多くのユーザーを惹きつけることができるのは当然ですが、ユーザー数の維持に関してはどうでしょうか。残念ながら、多くのDeFiプロジェクトは持続不可能なイールドファーミングを実施し、自分たちのガバナンストークンのインフレを通じて多額の報酬を発行し、そのプロジェクトのトークン保有者を犠牲にしながら、高利回りである一方、持続性のないAPY(年間利回り)をもたらしました。
関連:DeFi相場高騰の火付け役、イールドファーミングでは何が起こったのか|特徴と熱狂の理由を解説
NFT
2021年にDeFiの流行が一段落すると、ユーザーの注目はNFTに移りました。2017年当時、NFTをミント(生成)することは可能でしたが、技術的に難しく誰でも気軽に実行できるような状態ではありませんでした。2020年にRaribleなどのNFTマーケットプレイスが登場すると、ノーコードのNFTミントツールが使いやすくなりました。そして、Beepleなどの著名アーティストがNFTアートを1枚あたり数千万円もの価格で販売し、世界中のクリエイターがこの新しいメディアで収入を得ようとNFTに注目し始めたのは、2021年になってからのことでした。
PFP(プロフィール画像)に特化したプロジェクトは、NFTの普及をさらに拡大しました。同じ画像をプログラムで生成したバリエーションが1万枚も売れる例が数多くあるのに、なぜNFTアートは一度に1枚もしくは数枚しか売りに出されないのでしょうか?
良くも悪くも、Web3技術の金融化はそうした発展を加速させます。
関連:世界の投資家から注目を集める「NFTアート」とは|基本から購入・出品の方法まで解説
次なるWeb3要素は、DAOと分散型IDです。現在でも、こうした技術を使用したWeb3プロジェクトはたくさん存在します。しかし、DeFiやNFTとは異なり、DAOや分散型IDはまだ同規模での普及には至っておらず、それはこれらの技術が金融化されていないことが主な原因であると私は考えています。
DAOや分散型IDといった技術でユーザーがどのようにお金を稼げるのかが明らかになれば、DeFiやNFTのような流行のサイクルやそれに対応した調整が見られることになるでしょう。
このような金融化がどのようなものなのか、いくつかの例を見てみましょう。
DAO
コミュニティによる独自DAOの立ち上げをサポートするノーコード・ツールは数多くあります。例えば、分散型の提案形成と投票を行うSnapshotや、コミュニティの財務をマルチシグで管理するGnosisなどです。
現在のDAOにおいては、コミュニティメンバーはガバナンスの意思決定に投票したり、委員会を選出したり、マルチシグの署名者として奉仕したりすることで、組織としてのDAOに貢献しています。
しかし、彼らがDAOに費やした時間や貢献に対しては、どのように報酬されているのでしょうか。DAOに参加することが、その参加者にとって金銭的に持続可能であるということは、DAOが広く普及するための鍵となります。
関連:DAOのハードルを解消 信用スコアの仕組みとは|Ontology寄稿
そうした方法の1つは、報酬制度の標準化と自動化です。手動による報酬制度は、報酬の作成者が報酬の割り当てや請求フォームを書き出し、手動で確認を行い、支払いを行う必要があるため、煩雑な作業となります。仮に、DeFiプロジェクトが流動性プロバイダーを1人ずつ採用し、手作業でイールドファーミングの収益を配分していたら、DeFi市場がこれほど早く大きく成長することはなかったでしょう。
同様に、報酬制度も組み立てラインのように再設計する必要があります。報酬は、標準化され、投稿・検索・取得・確認・メインプロジェクトへの統合などが簡単に行えるようにしなければなりません。また、報酬を与える活動領域を見直し、通常の業務やよりミクロな業務も報酬の対象に含めるべきです。
ロゴのデザイン、提案への投票、ツイートのリツイート、委員会の委員として従事するなど、ジャンルや業務単価問わずに全ての業務がこうした報酬制度の中に組み込まれる必要があります。報酬が標準化され、プロセスが自動化されれば、イールドファーマーと同じように報酬目的でDAOに参加するユーザーが増加するはずです。
関連:DAOはWeb3における次のカギになる|Ontology寄稿
分散型ID
現在、データブローカーは毎日同意される無数の利用規約やプライバシーポリシーを通じて収集された人々のデータから、何十億ドルもの利益を得ています。また、データブローカーに自分のデータが販売されることを拒否できない場合も往々にしてあります。
分散型IDは、人・組織・モノに分散型識別子(DIDs)とそうしたIDに関するプロパティを格納するVC(Verifiable Credentials:検証可能な認証情報)を統合したシステムです。この新しい構造により、ユーザーは自身のデータを隠したり、必要時に選択的にデータを公開したり、さらにはデータへのアクセスに課金を促したりすることが可能となります。
こうしたデータのあり方の変化は、ユーザーによって新たなマネタイズ戦略の幕開けとなります。自身のデータを所有していれば、そのデータを直接販売することでユーザーは利益を得ることができます。例えば、調査やターゲット広告、研究などに協力する際に、自身のデータを同意の上で販売することで、ユーザーは収益を得られます。
分散型IDの規模拡大のためには、自動化プログラムを介したデータへのアクセスを可能にし、データの使用ごとにユーザーに料金が支払われるストリーミング決済を行うことが必要となります。このようなプロセスは、強固なWeb3のインフラなしでは実現できません。
データブローカーからデータを購入するよりも、コミュニティから直接データを購入する方が簡単でなければ、プロジェクトが分散型IDを採用する可能性は低くなります。またユーザーにとっても、ユーザーが自身のデータを記録し、好きなだけ多くの買い手に簡単に繰り返しデータを販売できるように仕組みを整える必要があります。
まとめ
Web3に関する技術は数多く存在し、それらを実装するプロジェクトもまた数多く存在しています。
こうした技術の「金融化」は、Web3の普及を後押しするための「すべて」ではありませんが、強力な推進力となります。Web3が適切に発展していくために、持続可能な形で正しく調整されたインセンティブを導入することに注力しなければなりません。
私たちはまだWeb3の初期段階にいるため、Web3が実現する未来がどのようなものなのかをやっと垣間見れるようになってきました。ここ数年のDeFiやNFTの例を見ることで、それがどのようなもので、そこに到達するために何が必要であるかを予測することは可能なのです。



 はじめての仮想通貨
はじめての仮想通貨 TOP
TOP 新着一覧
新着一覧 チャート
チャート 取引所
取引所 WebX
WebX



























































